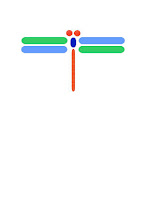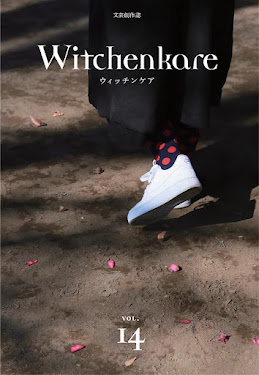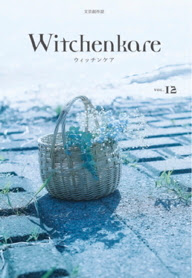ちょうど1年前の今日(2024年5月19日)は文学フリマ東京38の日でして、私(←発行人)は木村重樹さん、仲俣暁生さんと共同主宰で「ウィッチンケア書店」のブースにおりました。仲俣さんは「破船房」という個人レーベルでの本、『橋本治「再読」ノート』を携えて──ええと、話はさらに遡りますが、そのもう少し前、仲俣さんが「軽出版」という呼称で本格的に自作の本をつくって売ることにした、と伺ったとき、私はメールのやりとりで「それは黒船です!」などと書いていた記憶がありまして──そして、月日が流れ、今年の文学フリマ東京40。私と木村さんは「ウィッチンケア書店」として。隣席には仲俣さんの「破船房」ブース。おそらく破船房さん、弊ブースの数倍(それも片手じゃ数え切れないくらい...)の冊数を、世に送り出していたはずです。やはり黒船だった...いや、そのスタイルや走りの良さは、カーボンファイバー製のモーターボートかもしれない。すごいなぁ、と思うとともに、2010年から制作方法を変えていない小誌のダイナソー性(!?)にも、気付かされたのでした。
そんな仲俣さんの小誌今号への寄稿作は〈橋本治の書物観〉。冒頭では「破船房」というネーミングと橋本治の関係についても語られていまして、筆者にとって、橋本治がいかに重要な作家なのかが伝わってきます。また、橋本の著書『浮上せよと活字は言う 増補』(2002年)が平凡社より復刊され、追加された二本のエッセイのうちのひとつ「産業となった出版に未来を発見しても仕方がない」が、筆者の依頼した原稿であることも記されています。
作品後半では、仲俣さんが橋本治をインタビューしたさいの素敵なエピソードが。...これについては、みなさま、ぜひ小誌を手に取ってお確かめください。そして「破船房」さんの出版物については、BASEやPASSAGE by ALL REVIEWSのサイト(←リンクを貼ってます!)をご参照ください。
一九九三年の『浮上せよと活字は言う』で徹底的な「雑誌」批判を行った後、橋本は主戦場を書き下ろしの本に絞る。雑誌から書物へ。このシフトが意味するのは、自分の読者を同時代だけに求めず、時を超えて出会う未来の読者に委ねる姿勢ではなかったかと、いまこの文章を書きながら私は考えている。なぜなら私自身、そんな気持ちになりつつあるからだ。
~ウィッチンケア第15号掲載〈橋本治の書物観〉より引用~
仲俣暁生さん小誌バックナンバー掲載作品:〈父という謎〉(第3号)/〈国破れて〉(第4号)/〈ダイアリーとライブラリーのあいだに〉(第5号)/〈1985年のセンチメンタルジャーニー〉(第6号)/〈夏は「北しなの線」に乗って ~旧牟礼村・初訪問記〉(第7号)/〈忘れてしまっていたこと〉(第8号)/〈大切な本はいつも、家の外にあった〉(第9号& note版《ウィッチンケア文庫》)/〈最も孤独な長距離走者──橋本治さんへの私的追悼文〉(第10号)/〈テキストにタイムスタンプを押す〉(第11号)/〈青猫〉(第12号)/〈ホワイト・アルバム〉(第13号)/〈そっちはどうだい?〉(第14号)
※ウィッチンケア第15号は下記のリアル&ネット書店でお求めください!
【最新の媒体概要が下記で確認できます】
https://yoichijerry.tumblr.com/post/781043894583492608/