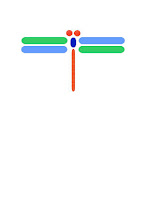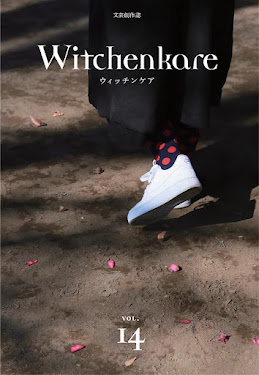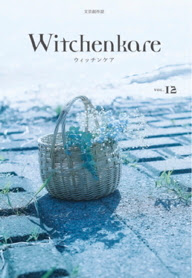はい。やっぱり、きちゃった。(8回連続)
……、感無量。もはや令和5年に彼女の「きちゃった」設定を続けること、棘の道なんだが、継続します。
「今年もできましたよ、ウィッチンケア第13号。持ってきたんだから、ちゃんと読んでね」
そう言って彼女は微笑み、燃えている果物が表紙になった本を差し出す。
「なんか、今回のは不穏なヴィジュアルだなぁ。13号...数字も不穏だ」
「そこは、あんまり気にしなくても大丈夫です。読めば前号よりさらにおもしろいから」
「自信満々だね」
「だって発行人、ルーティンになっちゃったら続けない、って言ってるし。発行したってことは、いままでで一番おもしろい本になった、ってことだと」
「わかりました。その言葉を信じて読みます。でっ、あのぅ、もし読まなかったら今年も?」
「もち、殺す」
もはやポリコレとかを超越した笑顔を見せて、彼女は去った。僕はウィッチンケア第13号をじっくり読み始める。
表紙、美しいがそこはかとなく不穏です。ロゴは第9号〜第11号とめまぐるしく変化し続けていたけれども、今号は第12号と同じ。前号でエディトリアル・デザインを手がけた太田明日香の、余白を活かした美意識に発行人が魅了され継続とした、と推察できる。ページを繰ると、表2はさらに不穏なモノクロ写真(人影?)。ロゴだけのシンプルな扉に続いて、見開きの「もくじ」。作品名より人の名前が上なのは、創刊以来変わっていない。次の見開きページは不穏ながらも可愛いらしい黒猫の写真...と、ここまで繰り返し「不穏」という言葉を出してきたが、とにかく、今号のヴィジュアルイメージを支配している写真家・千賀健史の作品については、別項の「写真家・千賀健史さんについて」を読んでもらうのが一番だと思う。
今号のトップは荻原魚雷。「社会恐怖症」をキーワードに人付き合いについて考察した一篇だが、文中の「麻雀で危険牌が通るか通らないかみたいな勘」という例えが胸を突く。続いての中野純は専門分野である闇についての、軽妙ながら大真面目な提言。野村佑香は自身のチャイドル時代を振り返りつつ、現在の〝推し〟との良好な関係を語る。私は「中森文化新聞」でチャイドルという言葉を知ったが、当時の関係者にこそ、ぜひ読んで欲しい一篇。初寄稿の加藤一陽は〝飲み散歩〟の楽しさを語りつつ、新しい世代の時代認識を垣間見せる。蜂本みさの小説もまた、若い世代の仕事観が伝わってくるシニカルな読後感。初寄稿となるコメカの「2010年代」への決別...その先もまたディストピアなのか、光が射しているのか? やはり初寄稿となる木俣冬の寄稿作は、タイトルからは推察できない、ある役者についての深い考察だ。久禮亮太は今春自身が開店させた書店についての、メイキング。今後独立系書店を目指す方には示唆に富んだ内容のはず。すずめ園の掌編小説は日常に宿る夢のような不可解さを選び抜かれた言葉で描いた。荒木優太は、今回は評論家というより作家的なスタンスの一篇でエントリー。美馬亜貴子は作品とそれを生み出す側と社会通念との微妙なバランスについての小説を。武田徹は鶴見俊輔と詩の関係性を、リカルシトランス(不可操性)という言葉を手掛かりに読み解く。久山めぐみは脚本家・坂元裕二の作品をそのメロドラマ的な特長に着目して考察。柳瀬博一は都会に生息するカワセミの環世界と、人にとって「いい街」の共通点についてのフィールドワーク。朝井麻由美は自身のテレビ番組出演経験をもとに、バラエティータレントの心性に思いを馳せる。武田砂鉄の疑似インタビューでは今回「プリミティブノミー」なる妖しい新語がキーワードとなっている。宇野津暢子は第11号に掲載した小説の続編、二人の関係性が〝危険〟水域に。多田洋一はレコード屋と音楽、そして〝書き換え〟を題材にした小説を。トミヤマユキコは変名を使うことによる人格やジェンダーの妙味を語る。長谷川町蔵は渋谷を舞台に、世代論を意識した小説を。小川たまかは京都での生活、そしてツイッターで巻き込まれたある事象について。吉田亮人は図書館での展示会を開催したことで感じた「写真集をつくるとこ」の意義を。谷亜ヒロコは育児とホス狂いの共通点を自身の体験をもとに探る。武藤充は先祖の来歴を現在の町田市と重ね合わせて検証した。久保憲司は人生の余命について、日本の経済政策の問題点を絡めながら小説化。仲俣暁生はビートルズの「ホワイト・アルバム」に至る、自身の音楽遍歴を振り返る。柴那典は試写会で感動した「エブエブ」等について、ジェネレーティブAIも使用してアカデミー賞 受賞前に早々とレビュー。清水伸宏は失踪した妻を探す男の心境を細やかに描いた。ふくだりょうこは祖母の死をきっかけに露見した家族の人間関係の掌編。矢野利裕は著書「学校するからだ」に収められなかったアナザーストーリーを。藤森陽子はお香の会への参加をきっかけに考えた自身の「ライター」という仕事について。木村重樹はいわゆる「鬼畜系」の捉え方が時代を経て変化していることへの雑感を。宮崎智之は自身の職能である「書くこと」について、あらためて多面的に考察した。東間嶺は今年になって物騒な話題を振りまいている、あの人気者も登場する戯曲を。かとうちあきは「大山鳴動して〜」なんて言葉も連想させる、ネズミにまつわる話。山本莉会はテキストの視覚的おもしろさも組み込んだ、十二支が登場する掌編小説。そして我妻俊樹の小説...言葉の万華鏡、イメージが拡散する不思議な世界へと誘われる。
37篇の書き下ろし後に、今号に関わった人のVOICEを掲載。その後にバックナンバー(創刊号~第12号)を紹介。新たにQRコードをつけたのでWitchenkare STOREでその場で購入できるとは、世の中便利になったものだ。……こんなに読み応えのある本が、じつはまた少し値上げして(本体:1,600円+税)でして、みなさまごめんなさい。諸物価高騰のおり、小誌を続けていくためのこととご理解くだされば嬉しく存じます。
それで、今回もまた繰り返すしかないのだが「ウィッチンケア」とは、なんともややこしい名前の本だ。とくに「ィ」と「ッ」が小文字なのは、書き間違いやすく検索などでも一苦労だろう。<ウッチンケア><ウイッチンケア><ウッチン・ケア>...まあ、漫才のサンドウィッチマンも<サンドイッチマン>ってよく書かれていそうだし、そもそも発刊時に「いままでなかった言葉の誌名にしよう」と思い立った発行人のせいなのだから...初志貫徹しかないだろう。「名前変えたら?」というアドバイスは、ありがたく「聞くだけ」にしておけばよい。
そしてそもそも「ウィッチンケア」とは「Kitchenware」の「k」と「W」を入れ替えたものなのだが、そのキッチンウェアはプリファブ・スプラウトが初めてアルバムを出した「Kitchenware Record」に由来する、と。やはりこのことは重ねて述べておきたい、とだんだん話が袋小路に陥ってきた(というか、いつも同じ)なので、このへんにて。