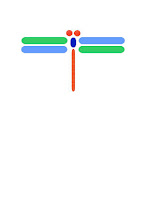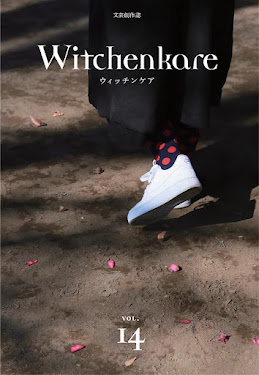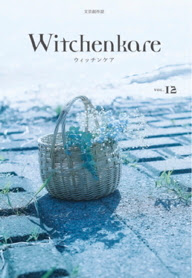前号がウィッチンケアへの初寄稿だったオルタナ旧市街さんは、昨年2冊の書籍を上梓されていまして、1冊は6月に刊行されたエッセイ集「踊る幽霊」(柏書房)。そして10月には、OHTABOOKSTANDでの連載に書き下ろしを加えたグルメ小説集「お口に合いませんでした」(太田出版)を。また筆名=誌名のネットプリントマガジンも、今月5日に最新の19号が配信されています。そんなオルタナ旧市街さんの小誌今号への寄稿作「氷を踏む」は、とにかく切れ味が鋭くて、前号への寄稿作「長い長いお医者さんの話」でのゆんるりっとした世界観(いや、前作は前作でそこはかとなく不安定さも漂ってはいたが)とは対象的。この振れ幅の大きい作風が筆者の魅力なのだな、と思いました...っていうか、もうちょっと個人的な印象を書きますと、筆者が「テキストを攻めている」感じが文章の端々から伝わってきて「面白さ」と「怖さ」が増幅されている、というか。うまく言い表せないのですが、まず読みやすさ/分かりやすさは持ち前のスキルでクリアしつつ、さらに「意味が通じるギリギリのところまでテキストを砥いで、結んで」、それで作品として成立させている、というか。これって詩の作法に近い!? ...すいません、↑のほうで“切れ味が鋭くて”と書いた理由を説明しようと思ったら、切れ味鈍い駄文になったかも(陳謝!)。
作品前半に〈なんの因果か、話しかけやすいタイプの人間なのだろう〉という一文があり、これはオルタナ旧市街さんが“好感度の高い人”として社会生活を送っている証左とも思えたのですが、しかしそれに続く文章が〈昔からよく道を聞かれたりマルチや宗教の勧誘に遭ったり道すがら他人にからかわれることがほんとうによくある〉と。「踊る幽霊」を拝読して、筆者は町で面白い光景によく出会うな、観察眼が鋭いからかな、などと呑気に感じていましたが、でも都会暮らしにおける「面白い」と「怖い」は紙一重、なのかも。
私たちがおそらく「ふだんは深く考えないようにしている」ことで成立している日常...その背景に存在する危うさについて、自身の体験をもとに、今作内では感度MAXまで考察してみました、という一篇だと私は読み取りました。さて、ではどうする? 明快な処方箋はなさそうですが、みなさま、ぜひ本作を読んで“氷の下(氷そのもの)”について、改めて意識してみてください!
※ウィッチンケア第15号は下記のリアル&ネット書店でお求めください!
【最新の媒体概要が下記で確認できます】
https://yoichijerry.tumblr.com/post/781043894583492608/