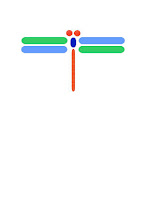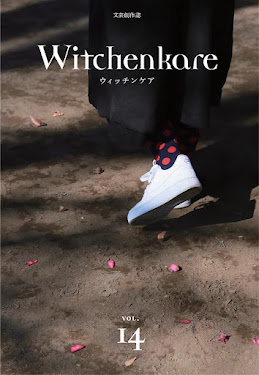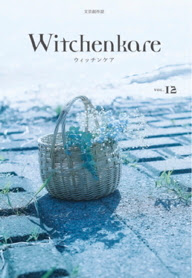昨年4月に発行したウィッチンケア第14号に掲載の掌篇小説「ゼロ」が、小誌への初寄稿作でありました3月クララさん。同作はいま読み返しても、日常感とSF感が絶妙なブレンドで洒落ています。私(←発行人)は今世紀になってからハリウッドの大作SFをほとんど観なくなっちゃったんで(理由は書き出すと長くなるので割愛...)、全然当てずっぽうな感想なんですが、たとえばイーサン・ホークとユマ・サーマンが出てた「ダカタ」とかみたいな、ほどよいスケールでの納まり具合が心地好い良作テイスト。筆者もそのくらいの風合いを狙って創作している感じがするんですよね。それで、そんな3月さんの小誌今号への一篇は、「ゼロ」のスピンオフ、というわけではないのですけれども、同根の事案(逸話)から派生することになってしまった、幽霊たちの話。訳あってお亡くなりになった「わたし」は、やはり幽霊となってしまった女性の部下・加島を事故現場で見つけて追跡したのですが、ちょっと、見るに堪えない光景を目の当たりにしちゃったりして...それで、やっぱり家族のことが一番心配、ということなので、幽霊として帰宅してみるのでした。
父親不在の家庭の様子を、父親ではあるが、しかし幽霊として眺める「わたし」...私は昨春実母を亡くしましたが、あの葬式の取り計らい方、預金通帳を解約して妹と分与したこと、糠床を放りっぱなしにしている状況などを、彼女が幽霊として家に戻ってきてどこかから眺めていたとしたら、それはかなり申し訳ない気持ちになりますが。。。
タイトル「ここから始まる」というのが、なかなかシニカル。それと3月さんは前作でも今作でも、登場霊物の行動規範に厳しい、というか、幽霊にできること/できないことをかなり細やかに描いていまして、たとえば「タクシーにただ乗りできるのはありがたいが、幽霊に行き先は決められない」とか。このあたりの匙加減が、本作のあり得なそうであり得そう感を醸成しているのだと思います。みなさま、ぜひ小誌を手に取って、なにが「始まる」のかお確かめください!
玄関には見覚えのある男物の靴が二足並んでいた。居間に入ると息子たちと妻が炬燵でくつろいでいた。初めてこの家から出す葬儀である。さぞかし右往左往していることだろうと冷やかすつもり帰ってきたが、予想に反してのんびりした雰囲気に、わたしは拍子抜けしてしまった。テーブルには食べ終わった夕飯の食器がそのままになっていた。
「お兄ちゃん、お父さんが帰ってきた」
妻は立ち上がるとわたしを通り抜けて玄関に向かった。
玄関のドアを開ける気配がしたあと、妻は怪訝な顔で居間に戻ると、仏壇を開いて蝋燭と線香に火を灯し、手を合わせた。
「お母さん、やめてよ。そういうスピリチュアルなノリ、お父さんが一番嫌ってたやつじゃない」
横になっていた長男がむっとした顔を隠すように、炬燵布団をあご先まで引き上げる。
3月クララさん小誌バックナンバー掲載作品:〈ゼロ〉(第14号)
【最新の媒体概要が下記で確認できます】