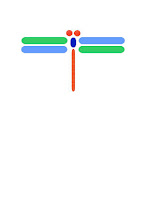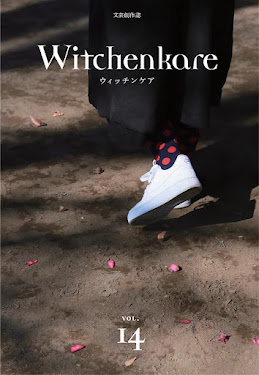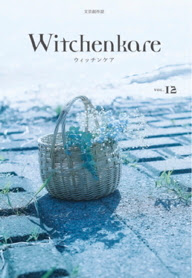ウィッチンケア第14号ではドナルド・フェイゲンの魅力について、多角的な視点で考察した「人工楽園としての音楽アルバム 〜ドナルド・フェイゲンとケニー・ヴァンス〜」という一篇をご寄稿くださった「DU BOOKS」の編集長・稲葉将樹さん。同作でのキーワードのひとつが、タイトルにも使われた〈人工楽園〉という言葉であったと思うのですが、誰かの背後にある〝それ〟を理解するためには、受け手側にもそれなりの教養というか学識というか、ざっくり言い表せばカルチャーみたいなものが備わっていることが必須であるように思われ、では稲葉さんの場合の〝それ〟はいったいいつ頃からどのように育まれたのだろう、などと思っていたら...小誌今号への寄稿作、本にまつわる筆者の文化的クロニクルとも言えそうな内容でして、興味深く拝読致しました。稲葉さんのご出身は〈茨城県の下妻市という ところで(大学浪人生として上京する1994年まで過ごした)、映画もヒットした嶽本のばら『下妻物語』の舞台で知られ「田んぼとヤンキー」で形容される町〉とのこと。市内には5件の書店があり、おもに小、中、高校時代にどんなを読んでいたのかが、詳しく語られています。
すごいな、と感じたのは、親しんだ本の内容(テキスト)はもちろんですが、出版社名やシリーズタイトル、さらに装幀、装画、挿絵なども含めての鮮明な思い出が記されていること。たとえばポプラ社の「少年探偵団」シリーズについてだと〈柳瀬茂の表紙は80年代でもレトロな戦前の面子のような配色で雰囲気があった〉。〈偕成社のシャーロック=ホームズ全集も当然のごとく読破したが、こちらは原著初版のシドニー・パジェットのイラストのままで良かった〉...私(←発行人)もホームズはたぶん全部読んだ記憶がありますが、イラストより謎解きだけに夢中だったような(無粋...)。本を「クリエイティブなフィジカル・アイテム」として受容していた稲葉さん、そりゃ蓄積される(文化的)情報、豊かなはずですよ。
作品後半では、5件の書店それぞれの特長も、個人的な思い出とともに語られています。なかでも4件目に紹介されている外山書店というのに、興味津々。〈ここはゲームブックの品ぞろえが豊富で、ミステリーやSFなどともに、アダルトなちょっと後ろ暗い趣味の本や雑誌も併売されていた〉...たしかに、私も小学生の頃、とある本屋(たぶん古本屋)に迷い込んで、アングラな漫画誌を手に取って、描かれた裸の男女が何をしているのかわからず目を見張ったこと、とかあるし。みなさま、ぜひ小誌を手に取って本作を読み、ご自身の本屋の記憶と重ね合わせてみてください。
※ウィッチンケア第15号は下記のリアル&ネット書店でお求めください!
【最新の媒体概要が下記で確認できます】
https://yoichijerry.tumblr.com/post/781043894583492608/