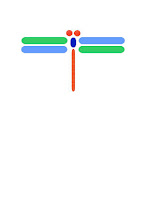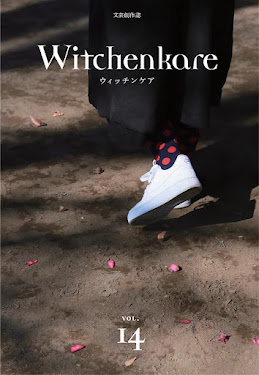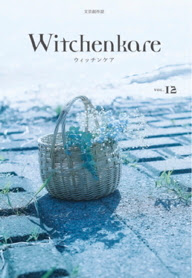文筆家/編集者として活躍する仲俣暁生さん。小誌では前号に続き自身が長らく抱えていたテーマを掘り下げた評論を寄稿してくれました。「国破れて」と題された作品は、昭和33年創刊の山岳誌「アルプ」、および同誌に近藤信行による評伝が連載された小島烏水を論じつつ、高度経済成長期から現在に至る「登山の商業化、大衆化」を独自の視点で考察したもの。作品冒頭で「登山はおろかアウトドア全般に興味のない私」「山岳書はもっとも縁遠い本のジャンルのひとつ」と表明する仲俣さんが、膨大な文献を読み込みながら登山、そして日本の風景にどんな感慨を持つに至ったのか。個人的には仲俣さんの近著「再起動せよと雑誌はいう」の読後感にも通じる、興味対象と自己(や存する社会)の来し方行く末を合わせ鏡にして思索を膨らませる語り口に、スリルを感じました(ぜひ本編をお読みください)!
本作に「ディレッタント」という言葉が2度登場したことは印象的。マイMacの辞書は「【(英)・(フランス)dilettante】芸術や学問を趣味として愛好する人。好事家(こうずか)。」と説明していますが、仲俣さんはたぶんこの言葉をたんなる「好事家」として肯定的には選んでおらず、それは「小島烏水という人自身が、文学史のなかではどうも収まりが悪いのだ。」という一節からも伝わってくるのですが、しかし仲俣さんは同時に「ディレッタントの立場」「ディレッタント的な存在」にはシンパシーすら持っているようでもあり...ううっ、長くなりそうなので、ここではこのへんで...。そして、最後に極私的蛇足。やはり本作に登場した「ヴェール・ドー」という言葉。どんな色なのか辞書で調べてもピンとこず、こういうときにインターネットは便利。「フランスの伝統色」というすてきなサイトを発見し、そればかりか「新しい部屋のドア、ペンキはこんな感じの色!」と勝手に決めたりしたのでしたw。
誤解を恐れずにいえば、「アルプ」は山の文芸誌だった。池内はそれを「アルプ王国」と呼び、「同じ体質の者の集まり」には「独特のくさみ」 があったことも言い忘れていない。もともと山に関心のない私としては、そうした雑誌のありかた自体が興味深かったし、アンソロジーの執筆者に辻まことや野尻抱影といった、多少なりと関心のある書き手の名をみつければ嬉しかった。
ただ池内の言うとおり、「アルプ」という雑誌のスタイルには強い魅力を感じながらも、同時にこのアンソロジーに収録された文章に対しては、全体としてなんともいえない距離感を抱いた。山について書かれた文章はなぜ、かくも文学的なのか。いつから日本人にとって山は「文学的」な場所になったのか。いや、もっと正直に言おう。なぜ、自分はここに書かれた文章に、さほど心を動かされないのか。その理由を知りたいという思いが、いつとはなしに自分のなかで膨らんでいた。
父方が信州の出身であるせいか、海よりは山のほうが肌が合う。子供の頃から、家族旅行ではよく山あいの地方に連れて行かれた。ただし父祖の地を実際に訪れたことはなく、父が亡くなった際に祖父の戸籍謄本を取り寄せるまで、在所の所番地さえ知らなかった。
それでも自分は山のある地方の人間だという感覚がどこかにあり、山の雑誌について小文を書いたことで、意識下にあったそれが発動したに違いない。山岳書や山の雑誌への関心は、書物史や出版史あるいは文学史上の関心にとどまらず、自分のルーツ探しともゆるやかにつながっていた。
http://yoichijerry.tumblr.com/post/46806261294/4-witchenkare-vol-4-4