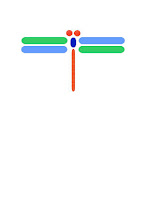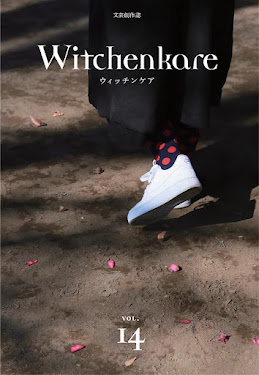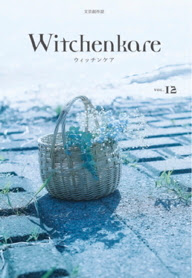ウィッチンケア第2号からの寄稿者・武田徹さんは、小誌では初回からずっと「詩」をテーマにした作品をご寄稿くださっています。いまや本の市場ではほぼ“幻の1冊”となってしまった第2号では、「詩について書くなら自らも詩を発表しなければ」と、自作の一篇も。そんな武田さんの小誌今号への寄稿作では、茨木のり子のあまり知られていない一面を考察、さらに《言葉の魂》(言葉には魂が宿る!?)について、ご自身の大学教員としての体験を交えて語っています。さて、茨木と言えば、たとえば詩集「見えない配達夫」(飯塚書店/1958年)に収録された「わたしが一番きれいだったとき」(わたしが一番きれいだったとき 街々はがらがら崩れていって とんでもないところから 青空なんかが見えたりした 〜)が国語の教科書に載るくらい有名な詩人で、その内容とメッセージは私(←発行人)のような凡庸な人間にもまっすぐに伝わってきまして...まさに戦後民主主義の良い面を象徴する、清廉潔白なイメージなのですが、武田さんが今回注目したのは、茨木の甥・宮崎治氏が遺品整理中に発見した未発表原稿をまとめた詩集「歳月」の中の、「夢」と題された一篇。
同作の一部を、武田さんのテキストより再引用してみます。〈おだやかに 執拗に わたくしの全身を浸してくる この世ならぬ充足感 のびのびとからだをひらいて 受け入れて じぶんの声にふと目覚める〉...たしかに、「わたしが一番きれいだったとき」などとは異質の、プライベート感が漂っているような。↑に記した“遺品整理中に発見した未発表原稿”は、茨木が「気恥ずかしい」という理由で生前には発表されなかった、とのこと。
この「歳月」という詩集に対する、ノンフィクション作家・後藤正治と谷川俊太郎の異なる評価、そして武田さんの見解も、本作の読みどころです。そして、《言葉の魂》についての、表題「いくじなしのむうちゃん!」とも絡んだ不思議な逸話...これについては、ぜひ小誌を手に取ってお確かめください!
茨木の家は住み手を失った今も昔のまま残る。保存に対する行政や地域、ファンの人たちの考え方を調査した卒論によれば、今後どうなるかはまだ未知数のようだが、茨木の場合、家はともかく、詩はよく残されている。人気があるからと言ってしまえば身も蓋もないが、多くの作品が今でも新刊書として入手可能だ。
~ウィッチンケア第15号掲載〈いくじなしのむうちゃん!〉より引用~
武田徹さん小誌バックナンバー掲載作品:〈終わりから始まりまで。〉(第2号)/〈お茶ノ水と前衛〉(第3号)/〈木蓮の花〉(第4号)/〈カメラ人類の誕生〉(第5号)/〈『末期の眼』から生まれる言葉〉(第6号&《note版ウィッチンケア文庫》〉/〈「寄る辺なさ」の確認〉(第7号)/〈宇多田ヒカルと日本語リズム〉(第8号)/〈『共同幻想論』がdisったもの〉(第9号)〈詩の言葉──「在ること」〉(第10号)/〈日本語の曖昧さと「無私」の言葉〉(第11号)/〈レベッカに魅せられて〉(第12号)/〈鶴見俊輔の詩 ~リカルシトランスに抗うもの~〉(第13号)/〈立花隆の詩〉(第14号)
※ウィッチンケア第15号は下記のリアル&ネット書店でお求めください!