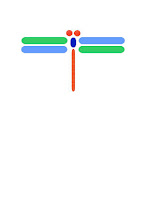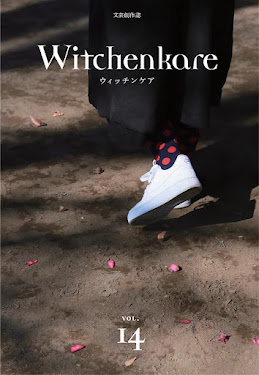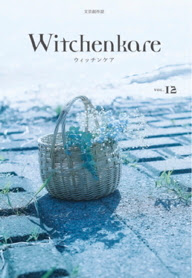仲俣暁生さんは小誌への初寄稿作「父という謎」(第3号掲載)以来、一貫して自分と家族のことをテーマ(の重要な要素)にした作品を届けてくださっています。編集者/ライター、さらに教育者として、活字メディアの分野ではほぼオールラウンダーな活躍をしている仲俣さん。SNSでも気さくに“会話”に応じてくれ、そこではけっこうご自身の来し方について、影響を受けた書物や音楽について、話している印象がありますが、書籍としてまとまったものとなると...個人的にはウィッチンケアでのこれまでの掲載作、現在は仲俣さんのnoteに転載されている「下北沢ノート」など過去にウェブで発表した作品などを再構成したエッセイ...いやコラム...いやいや、敢えて言えば「雑文」集のような本があれば、ぜひ読んでみたいと思います。個人の体験が普遍性を帯びて、昭和後期〜平成〜令和の文化事象全般(とくに本や音楽)を見渡す指針になりそうな予感。...そんな仲俣さんの今号への一篇は、これまでにも増して「自分語り」的要素が多めで、ちょっと、私小説を読んでいるような味わいも。引っ越し/ひとり暮らし/家族との生活という生活様式の変遷と、それに付随した愛着のあるモノ。最終的には本の話がメインですが、ギターやLPレコード、自転車についての話もおもしろくて。
本作でとくに印象に残ったのは「そのときどきの自分の興味関心の変遷の記録」という、「いま私の部屋、そして家のあちこちにある本」についての一文でした。この感覚は作品の前半で取り上げられている、いまはもう手元にはないが記憶には刻まれている様々なモノ(や体験)に対しても同じなのではないかな、と。たとえば「ペイル・ファウンテンズのファースト」は「旅先の金沢のレコード屋で出会」った記憶と紐付いていることが大事。さらに「カセットで買って聴きながら街を歩いた」ことがもっと大事、みたいな。でも、だとすると、冒頭と中盤に出てくる「いったいどこで間違えたんだろうか」という自問は、単に本が増えて身動きがとれないことに対するものではないはずで。
終盤になって登場する萩原朔太郎の第2詩集(大正12年)が今号寄稿作のタイトルであること。その詩集にまつわる母親との逸話が語られていること。ご自身が十八歳のころ「詩人になること」を夢みていたこと。...こんな読み方はきっと間違っているでしょうが、仲俣さんの今作は《いずれいつか書かれるかもしれない仲俣さんの自伝的私小説》のイントロダクションなのじゃないか、とも思えてしまいました。「いったいどこで間違えたんだろうか」の“答え”は、その「いまはまだ存在しない作品」の中で明かされるのかもしれない、と。
ウェブサイトでリンク先のページをクリックするように、ある本を読んで、興味をもったことがらに関わる本があれば、ついネットで検索して買ってしまう。そのログとして、リアルな本が手元に残る。いま自分のまわりにある本は、かつての自分の興味や関心、あるいは野心や探究心の残骸にすぎない。その残骸のなかで、まだ新しい本を読みたいと思い、自分でも書こうとするのはなぜだろう。
〜ウィッチンケア第12号〈青猫〉(P086〜P091)より引用〜
仲俣暁生さん小誌バックナンバー掲載作品:〈父という謎〉(第3号)/〈国破れて〉(第4号)/〈ダイアリーとライブラリーのあいだに〉(第5号)/〈1985年のセンチメンタルジャーニー〉(第6号)/〈夏は「北しなの線」に乗って 〜旧牟礼村・初訪問記〉(第7号)/〈忘れてしまっていたこと〉(第8号)/〈大切な本はいつも、家の外にあった〉(第9号& note版《ウィッチンケア文庫》)/〈最も孤独な長距離走者──橋本治さんへの私的追悼文〉(第10号)/〈テキストにタイムスタンプを押す〉(第11号)
【最新の媒体概要が下記で確認できます】