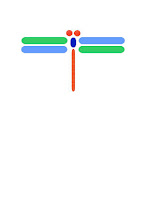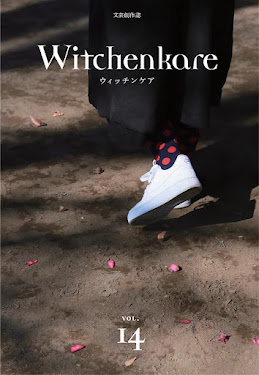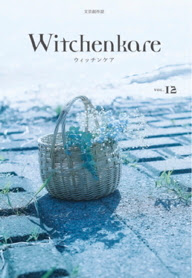住処のこと...<夜中に仕事をしていて行き詰まると、たまに不動産屋のホームページを見る>という一文に実感がこもっているように思えました。荻原さんの今作での主題は、賃貸住宅での生活をマイホーム(終の住処)での生活に替えるとして、自分にはどんな選択肢があるのか? についての考察。それを考えるトリガーとなったらしい、ある不動産広告のキャッチコピー(「何ひとつ諦めたくない」〜冒頭と末尾に2度登場)をググりました。出た! 地下鉄で大手町へ9分の新築物件。3LDKの賃貸が25万、買うと8000万くらいの。...あっ、荻原さんは「ここに住みたい」と思ったのではなく、このコピー(と、たぶん付随したスペックも)が喚起するなにかに平常心を侵食され、<何ともいえない気分になった>、と。
故郷で一人暮らしをするお母様が病に倒れたこと(現在は回復なさったそう)。お母様名義のマンションのこと。ネット検索で浮かび上がる、伊豆や熱海や桐生や足利や甲府の、100万円台で売り出されているワンルームマンション...。中央線沿線での生活が長くなった荻原さんにとっての、納得のいく<終の住処>とは、どこのどんな家なのか? 巡る思いのプロセスを、ぜひ小誌を手にとって追体験してみてください。
本作について、荻原さんがご自身のブログで紹介してくださっています。そのなかで<エッセイと私小説はどうちがうのかということを考えていたのだが、わからずじまい。自己申告で決めるものなのかもしれない><いつもとちがう文体に挑戦してうまくいかず、いつもどおりの書き方に戻した>と記していますが、私が最初にお原稿を読んだ印象、じつは「小説なのかな?」だったのでした。たとえば、お母様にまつわることと、「エアコンのリモコン」「ファミコンのソフト」の配置バランス(重さの比重?)が、<わたし>の主観を優先した、創作作品のように感じられた...というか。
買うかどうかはさておき、マイホームはまったく手の届かない夢ではない。
生まれ育ちは長屋だったが、わたしが上京した年に、突然、母が分譲マンションの一室を買った。わたしも父も寝耳に水だった。というのも、当時、父は単身赴任中で埼玉の工場に勤めていた。
一九八九年──バブルの最盛期だったから、首都圏に家を買うことはできなかっただろうが「なんで家族三人のうち、二人がいないときに家、買っちゃうかなあ」とおもった。母がマンションを買ってしばらくして、父は鈴鹿の工場に戻り、新しい家で両親が暮らすようになった。二十代のころのわたしは、その家にほとんど帰らなかった(大学を中退し、フリーライターになったことで、親との関係がこじれていた)。
二年前、父が七十四歳で亡くなり、マンションの名義を母に変更した。今のところ、資産価値はゼロではないらしいが、「負動産」まっしぐらの物件である。
母は「面倒やから、あんたの名義にしとくか」といったが、断った。正直、酒と煙草が大好きだった父とちがって、母は長生きしそうだとおもった。ヘタしたら自分よりも。
ウィッチンケア第9号「終の住処の話」(P096〜P100)より引用
goo.gl/QfxPxf
荻原魚雷さん小誌バックナンバー掲載作品
「わたしがアナキストだったころ」(第8号)
http://amzn.to/1BeVT7Y