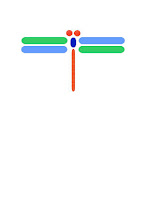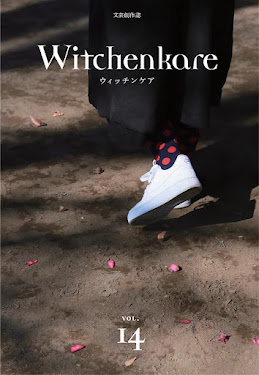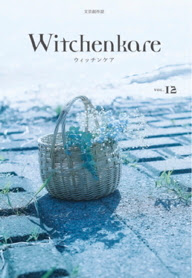寄稿作の<極私的「35歳問題」>は、日頃さまざまな社会事象をクールな視点で分析してきた宮崎さんが、その目を自分自身に向け、率直に思うところを綴った自伝的とも言えるエッセイ。タイトルにもあるように極私的な内容なのですが、しかし私はその飾らない語り口にある種のポップさ(代入可能な普遍性)を感じ、ぜひこの一篇を今号のトップバッターにと思ったのでした(これは「みんな」の、いや「あなた」のことではありませんか!? みたいな)。
作品内では村上春樹の「プールサイド」、東浩紀の「クォンタム・ファミリーズ」という小説で描かれた<35歳>が参照されています。ここで要約してしまうのはもったいない、ある程度の字数が必要となる丁寧な考察がなされていますので、ぜひとも多くの方に、本篇をじっくり読んでもらいたく存じます。...そうだ、私の極私的な<35歳>作品として思い出すのは、20代の終わりに観た金子正次脚本の「チ・ン・ピ・ラ」という映画。記憶だけで書いてますが、たしかジョニー大蔵扮する半チクなヤクザが東急百貨店東横店の屋上で「オレもう35歳だし」とぼやいていた、その切ない光景が啓示的で忘れられません。
35歳。いまの私はそこからさらに四半世紀も生き存えてしまいましたが(昨今話題の福田淳一さんと同い年!)、あの頃抱えていた焦燥感のようなものは、不惑になっても消えなかったし、いまも内在しているような気も。多少それを飼い慣らす術は覚えたかも。でも、いつそれに手を噛まれるかもわからんし...と、だんだん意味不明な自問自答に陥ってしまいまして、失礼。とにかく、まだ少年の面影を備え、どんな服でもかっこよく着こなせそうなルックスの宮崎さんが、こんなに真摯にご自身の人生と向き合っていることに、ぐっときてしまったのでした(いつか、宮崎さんの一人称の小説など、読んでみたくなった)。
学生運動に没頭し、何度か留年した後に苦労して就職した父は、昔の人にしてはやや遅れて母と結婚した。ぼくは、父が36歳の時に生まれた子どもだ。つまり、父がぼくを授かった年齢と、父が亡くなった時のぼくの年齢とは、ほぼ一緒なのである。
思えば奇妙な偶然だ。ぼくの視点からしてみると、父はまるでぼくにバトンタッチをするかのように、亡くなっていったような感覚がある。父が36歳の時にぼくが生まれ、ぼくがその時の父と同じ年齢になる直前で父は旅立っていった。しかも、それと同じタイミングで、ぼくは二度目の結婚をした。否が応でも重ね合わせて考えてしまう。
仮に、ぼくが父の年齢まで生きるとしたら、ちょうど人生の半分を終えたことになる。父がぼくの「父」となった同じ年月を、これから歩んでいくのだ。もちろん、もっと長く生きるかもしれないし、もしかしたらもっと短い人生かもしれない。それは誰にもわからない。しかし、35歳という年齢と、父が亡くなった年齢を対照させて、そこに意味を見出してしまうのは、人間の性なのであろう。
ウィッチンケア第9号<極私的「35歳問題」>(P004〜P009)より引用
goo.gl/QfxPxf
http://amzn.to/1BeVT7Y