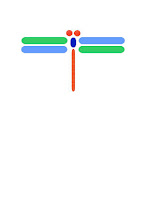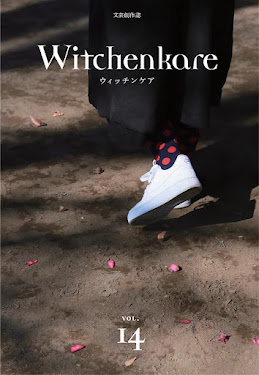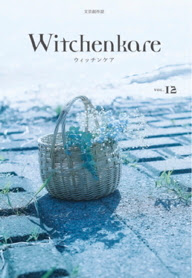下北沢の書店B&Bにて武田徹さんと仲俣暁生さんの対談がおこなわれました。イベントのタイトルは「“答え”が出なくても、とことん語ってみる! 〜ノンフィクションの書き手として、いま言葉にしたい幾つかの事柄〜」という、なんともわかりにくいもの。事前取材してくれた下北沢経済新聞のインタビューで仲俣さんが「このテーマでどれぐらいの観客が来るのか楽しみでもあります(笑)」と語ったように、いったいどんな方が関心を持ってくださるのか? 正直、言い出しっぺの私も一抹の不安を抱えていましたが、結果は予約席ソールドアウト/当日券売り切れの大盛況。客席との質疑も白熱し、予定の2時間を1時間近く超過した長丁場となりました。
以下は当日の、極私的レポート(文責・多田洋一)。
3.11をどう体験したのか?
2人の話は3.11に関する個人的な体験から始まった。武田さんは新著「原発論議はなぜ不毛なのか」でも書かれているように、東日本大震災の揺れを体感してはおらず(搭乗した成田空港発の航空機が離陸予定時間の27分後に地震発生。つまり実際に離陸してすぐの発生だったのではないかと想像される)、事態を知ったのはイスタンブールに到着してから。その後はインターネットを中心に情報を追い、もっとも衝撃を受けたのは福島第一原子力発電所一号機の水蒸気爆発だった。
対する仲俣さんは自宅にいて、NHKの国会中継をBGVに仕事を進めていた最中に速報のテロップが目に入り、その後は東北地方が震源との情報を得たうえで、すぐに始まるはずの揺れを待ち構えていた。
「本棚が崩れ家族が帰宅難民になりしましたが、自分の身は安全という立場で、その後の情報を追っていました。津波で多くの人が亡くなっているが渦中の人々には情報すら伝わってないはず、と思いながらも、でもどこか傍観者のように震災に接してしまった。そのことに対する意識が、以後のものの考え方や書くことに影響したと思います」(仲俣さん)
「私は一生3.11を経験できないまま居続けなければいけない、ということが後になってしみじみわかってきました。具体的に言うと、日本でのリアルタイム報道ではなくネット上のテキストデータに接していたので、帰国後に震災直後の新聞を見て驚きました。テキストだけで知ったことと、紙面にレイアウトされて伝わってくることは感情面でも大きく違うと思います。いま考えれば、自分は日本から離れていたことで、冷静に“装いなしの情報”だけを受け止めていたのでしょう」(武田さん)
武田さんが帰国したのは3月16日。学生部長を務める恵泉女学園大学の卒業式も中止となり、そのまま海外に留まることも可能だったが、日本に残した両親や学生に対する思いだけでなく、「早く戦線復帰しなければいけない」という倫理感が強く働いた。国内では福島第一原発の深刻な状況が伝えられ、過去の取材で少量ではあるが被爆体験してきた慣れがあって、放射線量に対して普通の人とは少しバイアスが違った武田さんでも、雨が降れば嫌な気持ちになる日々が続く。
だが、そんな個人的感覚とはべつに「いまはこれを言わなければ」との思いから“政治的な見解”をメディアに発表する。それは「この状況であれば臨界爆発はしない」というものであった。おそらく正しい、しかし、絶対正しいか? と問われれば自身でも確証はなかった。ただ日本の軽水炉の仕組みを知っている者として、臨界のしにくさを伝え、冷静さを社会に取り戻させることが現況における自分の義務ではないかと決断して書いた。
その頃の仲俣さんは氾濫する情報に翻弄されないため、いくつかの決め事を自分に課す。ある種の賭けでもあったが、まずNHKの報道はとりあえず本当だと信じよう、と決めた。そして自分の考えを固める手段として、震災前に書かれたテキストを読もう、と。
数々の文献を読み進めるなか小田光雄氏のブログを介して出会ったのが、阪神淡路大震災について書かれた外岡秀俊氏の「地震と社会」という本だった。「3.11後、あらためて自分は関西で起きた大震災にリアリティを感じていなかったことに気づいた」と、仲俣さんは敢えて口にする(それは東日本大震災への、地域による温度差を自分に引き寄せた発言、と受け取れた)。
同書を読むことで、過去の震災体験が今回も活かされなかったこと、また「なにが書かれているか」だけでなく「いつ書かれたか」というタイムスタンプによって言葉の意味と機能が違ってくることを仲俣さんは実感した。
共同体に対する問題意識が出発点
阪神淡路大震災時、武田さんは当時連載していた月刊誌の記者として現地を訪ねるなど、何度か取材をした。その体験は「自分にできないことの多さを痛感させられた記憶」として残っている。雑誌記事の書き手としてできたのは「訪ねていき、取材して書くこと」。もちろん記事としての最善は尽くしたのだが、なにかやり切れてないような、うまくいかなかった思いがあった。
「その年の12月に『偽満州国論』を出版。その後『「隔離」という病い——近代日本の医療空間』でハンセン病を扱い、次に『核論』へという、自分としてはひとつながりの仕事を手がけ始めた時期です。枠組みを意識しつつ、現象をもう一度位置づける、といったスタイルで書くほうが自分は社会に貢献できるのではないか? 震災にまつわる雑誌記者としての経験も手伝って、以後の方向性を見出したように思っています。外岡さんの本も物事の全体像を描こうとしていて、それはとても健全なジャーナリズムだと思います。もちろん雑誌の1回の取材で全体像を描くことだって可能かもしれないが、当時の私にはそれはできなかった。物事の全体像を、たとえば哲学などと接続して再評価するようなやり方のほうが自分の能力を活かせるのではないか、と考えさせられたきっかけのひとつだったように思います」(武田さん)
「武田さんの方法論や社会に対する役割の果たし方、同時に一貫したテーマ設定などは、結果として3.11が包括するできごとになってしまいましたが、読者は満州国、ハンセン病、核、原子力が同じモチーフだとは、今回のようなことが起こらなければ気づかなかったかもしれませんね」(仲俣さん)
「ずっと同じことをやっているつもりなのです。自分には共同体に対する問題意識があり、『偽満州国論』では敢えて時空的に遠いところをモデルにし、逆にそこから照らし返して日本社会を考えてみた。次はハンセン病療養所という、日本にありながら異界のような場所に照らし合わせて日本社会を考える。それからちょっと欲を出して、いまの日本社会を考えるために原子力というテーマを選んだのが『核論』で、社会に起こる分断や隔離を確認する仕事だったと思っています。『核論』のなかでは『そうではない道を目指すべきではないか』と仄めかして書いたつもりなのですが、しかし3.11は結果として社会を一段と激しく分断させた。ハンセン病に取り組んで強く感じたことで、これは言い過ぎかもしれませんが、分断や差別というのは人間の業なのか、というある種の達観さえ持ちました。しかし、だとすればそこを認めたうえで対話の仕組みを考えていかなければ、との思いで仮説を立てていくのが自分の仕事だと思っています」(武田さん)
この後、仲俣さんに「かなり挑戦的なタイトル」と評された武田さんの新著「原発論議はなぜ不毛なのか」の出版経緯について説明があった。
3.11後に「私たちはこうして『原発大国』を選んだ-増補版『核』論
」と改題された『核論』は、単行本〜文庫〜新書という3種類のパッケージ化を経た作品だが、さらに2年を経て電子書籍化する話が持ち上がった。
武田さんはそのつどあとがきも時代を意識して書いてきたが、電子化に際して3.11後に発表した原稿もまとめて付録にしようと整理してみた。すると、それだけでもけっこうな分量あり、であれば各原稿の時間軸を明らかにし、さらに自身の日記のような書き下ろしも加えて新たな本にすることにしたという。「タイトルについては、書き下ろした終章部分を読んだ編集者のアイデアを活かして付けました」と武田さん。日記部分には震災後、シンポジウムなどでボコボコに叩かれた際の心情などが率直に書かれており、そのあたりを察した編集者が「不毛」という言葉を思いついたのだろう、と。「私自身は、対話には終わりがなく、ずっと続いていくものという考えですので、この本が出たことにより論議が不毛なのかどうか継続して考えるきっかけになればいいと思います」
不可知な領域の判断、もの書きとしての立場
対話は原発問題から科学技術の発展や経済、政治の分野へと広がっていく。「放射能の影響に限らず、たとえばアベノミクスやTPPについても、合理的なようで不毛な論議がネットで交わされ、自分には判断できないことが増えた」と語る仲俣さんに、同意しつつも武田さんは「わかっていることと不可知な領域の関係を、うまく取り分けながら議論を深めることが大事。人々が思考や判断を要請されている状況なのは間違いなく、分断も深刻だが、でもその先に希望があると信じたい」と考え続けることの大切さを解く。議題は情報の送り手でもある自分、もの書きとしての立場へと移行していく。
「専門家ではない人が専門以外の領域について発言しても強い影響力があることが、震災後に可視化された。それが事実かどうかは不明でも、実感のレベルで機能してしまうという、ある種のポピュリズム。そうした言説が蔓延していることで、たとえば武田さんは既存メディアに対する不信感や絶望感のようなものを持ったことはありませんか? 書き手のなかには『これからはメルマガや電子書籍で読者とダイレクトに』といった考え方になった人もいるような時代ですが」(仲俣さん)
「僕は0か100か、みたいな考え方はしてきませんでした。もの書きの中は『この出版社からしか出さない』というように活動を固定する人もいますが、私は幸か不幸かあまり売れてこなかったので、ひとつの出版社から本を出すとたいてい次には出せない状況になる。焼き畑農業方式というか、出版社やメディアを転々としながら自分の言説をつくってきた。そんな経験から言えば、既存メディアに対する不信感、という心情もわかるが、すべてと縁を切る必要はないと思います。あるメディアですべてが言えるわけでもないが、この部分は信頼できる、使える、といった見方で関係を繋げていたほうが得だと思うし、マルチメディア的な“たすき掛け”の考え方でやっています」(武田さん)
ジャーナリズムとノンフィクション、そして詩へのリスペクト
武田さんは1958年生まれ、仲俣さんは1964年生まれ。書き手としては後輩の立場となる仲俣さんは今回、対談の進行において先輩の武田さんに思いをぶつける、という役割を担ってくれた。
そんな仲俣さんが今回ぜひ武田さんに尋ねてみたかったのは、ジャーナリズムとノンフィクションの違いについてだ。「武田さんは自分をジャーナリストとノンフィクション作家、どっちだと思っています?」と切り出した仲俣さんに、武田さんは「その違いにどれくらいの意味があるのかがわからない」と。そうですか、と受けた仲俣さんだが、より議論を深めるため、具体的な作家名や作品を持ち出して、さらに武田さんの真意を探る。
「佐野眞一氏の作品を僕はけっこう読んでいて、批判があるのは知っていますが、ノンフィクション作家として面白いと思っています。広い意味での“文芸”として作品に接しているから、事実的にどうなのかと感じても『文学だから、まあいいや』と。その点では、武田さんの作品は、ウィッチンケアに書いたものを除くとひじょうにドライですよね」(仲俣さん)
「……ああ、そうですね。『ウィッチンケア第2号』で私は詩を書いたんですよね。そして『原発報道とメディア』では、詩についての個人的に秘密してきた話をちょっと種明かししました。実は私は詩人になりたかった時期があり、実際に書いてもいました。ただ、詩の力とは言葉の力そのものだ、と私は考えていて、その力を抑えないと伝わらないこともある。言葉そのものが存在感を持ってしまうことで、言葉に意味を乗せて伝えることができなくなる。そこは相反するものだと。それで、やっぱり事実を伝えるものを書こうとすると、詩的な言葉の力を抑えなければと思いました。言葉の詩的な力はなんなのだろうと考えたのが私の卒論であり修論でもありましたし。言葉をメディアとして飼い慣らし、事実を伝えるために伝えられるか、ということを長く考えていた経緯があるのです。だから、さきほどのノンフィクションやジャーナリズムについて言うと、私にとっては詩から一番遠いものがジャーナリズムということになります」(武田さん)
それはわかるなぁ、と同意した仲俣さんは、飲み物をジンジャエールからビールへと切り替えた。武田さんの話はさらに続く。
「ただそれは理念としてのジャーナリズムであり、現実のジャーナリズムはそれほど詩から遠くない。感情を喚起する言葉そのものの力に頼っている。さらに言えば日本のノンフィクションはより文芸的だし、作品に文学性を求める傾向が主流になっていると思います。ルポルタージュという言葉は1937年にフランス語として日本に入ってきましたが、その言葉に対応していた日本語は記録文学、あるいは報告文学でした。このようにルポルタージュを『事実関係を、文学性を持って伝える』と定義してきた歴史が日本にはあります。ノンフィクションという言葉については1960年から刊行された筑摩書房の『世界ノンフィクション全集』が普及するうえで大きな影響を持っていて、その後、文藝春秋の『大宅壮一ノンフィクション賞』が創設され、自立したジャンルとなっていきました。1970年代以降、日本のノンフィクションは文芸的な傾向に向かい、調べてみると筑摩の全集にはけっこう科学的に整合性を求める作品も収められていたのだが、だんだんそういうものが落ちて、文芸ノンフィクション的なものが残っていったという経緯があるようです。こうしてみてゆくとジャーナリズムよりさらに文学性を高くもつようになっていったのがノンフィクションであり、つまりより詩に近い。私は詩から遠く離れたかったのでノンフィクション作家と言われるとちょっとどうかな、と思うところはあります」(武田さん)
武田さんは若い頃にノンフィクション的な作品を読んでいましたか、と尋ねた仲俣さん。武田さんの答えは「むしろ文学的なものが好きで、だから遠ざかろうとした」であった。
「僕は文芸評論家でもありますが、いわゆる団塊の世代が学生運動や政治に対する距離感を、小説という形式で書き始めたことに興味を持っています。一番わかりやすい例は村上春樹や高橋源一郎ですが、彼等が政治というものをデモーニッシュなものと捉えて距離を置いたり格闘したりすることを、面白いと思っていました。そして、僕と武田さんの共通点として言うと、僕もまた詩を尊敬する気持ちを持った最後のほうの世代なのです。高校生の時は『現代詩手帖』に投稿していたし、詩人は一番偉い、詩人になりたいと思っていました。小説家は、ちょっと落ちるけど詩人の次くらいに偉い、それ以外はなんか、よくわからないけど普通の人なんだと。……それで、気がついたら編集者になっていました。僕もまた詩の持つ言葉のごりっとした力を感じていた世代だったと、武田さんと話していて思い出しました。そして僕は団塊の世代の私ノンフィクション、みたいな作品がちょっと嫌いだったんですね。つまり沢木耕太郎以降の、ウェットな感じのものはずっと苦手、四畳半フォークみたいだなと思っていて、だから僕はポストモダン世代の村上春樹などの小説に惹かれたのだと思います。対して武田さんのようにどっぷり文学のなかにいた人がドライなノンフィクションにいくなんて、いったいなにがあったのでしょうか? たとえば失恋したとか?」(仲俣さん)
「いやぁ(苦笑)。たしかに遠ざかったのですが……。私が最初にノンフィクション的なものを書いたのは文藝春秋のムックでした。ホブソンズというアイスクリーム屋さんの流行現象分析のために、六本木から西麻布の交差点まで歩数を計るというものでした。当時、ジャーナリズムは靴底を減らし足で稼ぐというように言われていたので、それに対するアイロニーというか、足で稼ぐのがジャーナリズムなら、歩数で分析すればそれらしいかな、と。でもこれはひとつの象徴ですが、私のジャーナリズム的な仕事の動機はつねに方法に意識的で、どう方法を料理するか、なのです。だからノンフィクションにどっぷりと、純粋に現実社会を相手にしているということもなくて、いつも方法論的な関心に動機づけられてものを書いているというところがあります」(武田さん)
「もうひとつ伺いたいのは、文体や人称についてです。詩は韻文ですから、多くの人にとってもそれがなんであるかがわかりますが、散文となると、小説なのかノンフィクションなのか単なる嘘なのかわからなくなってしまう。書き手だって、そこを揺らがせながら書いていくことはあると思います。武田さんはこれまで、そして今後でも、どんな種類の文章を書いていくのが分断を乗り越えて機能する文章だと思っていますか?」(仲俣さん)
「テーマによって文体、そして人称を変えることは必要だと思っています。それがうまいのは、先ほど仲俣さんは苦手と言ったけど、沢木耕太郎は私にとっては大いに参考になる書き手です。沢木は人称や形式に対して方法論的に意識している書き手だと思うからです。ただ彼の場合、パブリックイメージはその正反対で、ファンは、彼のこと純粋なノンフィクション作家だと見て焦がれる。そこがうまいな、と。私は足で稼げと言われれば歩数を数えてしまうのでそういうことができなくて、……でも読者と一体感を求めることが書き手の目的だとは思えない。読者と一体化するより、最後にぶれたいという気持ちがある。……そういえばある編集者から、僕の文章は仲俣さんと似ているって言われたことがありますよ(笑)」(武田さん)
文体についての話が続き、そのなかで2人の出会いはかつて仲俣さんが編集者を務めていた「本とコンピュータ」であったこと、おたがいガジェット好きという共通点があること、Facebookでの書き込みに共感し合うことが少なくないことなども語られた。「文章が似ているというより、考え方のパターンに共通性があるのかもしれないですね」と武田さん。仲俣さんは「今日はもっと緊迫感のある、武田さんと僕の相容れないところを見出したいと思って臨んでいるんですけれどね」と笑顔を交えつつ、対談はさらに進む。
事実や人の言葉はそのままで面白いのか!?
今回のイベントは前後半の2部構成で各1時間。10分遅れでスタートしたこともあり、つねに時計が気になっていた。すでに、9時半近く。80分を越えても2人の会話に割り入れるタイミングすらつかめない。会場であるB&Bの店名は、BOOKとBEERの頭文字を冠したもの。白熱した論議から目が離せないお客さんも、喉が渇いてビールをおかわりしたかったり、トイレタイムが必要だったりしないかな? そしてなにより、このままでは予定時間を確実にオーバーしてしまいそうだし。
しかし、そろそろ一区切りをと思っていたのは、私だけなのかもしれなかった。壇上では仲俣さんが「僕は武田さんに文芸的な、ノンフィクション作家と言われてもいいような類の大著を書いてほしいと思っている。それは、もしかすると自分も書きたいからなのかもしれない」と要望し、その言葉に武田さんがやや口ごもりながら「じつは『こう落とせば読者は泣くだろうな』という書き方も、わかるんだけど」と反応していた。「えっ!? わかるんですか。それは聞き捨てなりませんね(笑)。じゃあ、書いてみて、と言いたくなりますけど」と速攻で突っ込む仲俣さんに「いや、だからやっちゃいけないんです」と武田さん。会場の雰囲気も、その後のやりとりを見守っている感じで、時計から目を離した。
「私はそういう書き方は罪だと思いますね。そこで、感動の共有で終わってしまうから、それ以上考えを進められないのです。思考のきっかけは共有ではなく差異であるはず。なにか違う、と思わせなければ読者はその先に行けないのだから、書き手の使命として共感で終わらせるのは罪深いのではないか、とも考えているのです」(武田さん)
「でもそういう社会に対して責任を果たすというもの書きとしてではなく、文学に対する未練や野心なども含めて、一度こんな小説を書いて死ねるんだったらやってみたい、みたいな気持ちはないんですか?」(仲俣さん)
「小説を書きたいという気持ちは、ずっと潜在的にあります。ただ、まだ早いと思っている。じつは2冊目の単行本(『イッツ・オンリー・ロックンロール・ジャーナリズム』)にまとめた連載では編集担当者の菅付雅信さんと毎回いかに“感動的な終わらせ方”にするか議論した経験があり、教わることも多かったです。でも自分のなかではそうした情感をあえて相手取る手法は彼と仕事したときにある程度考えてみたつもりなので、しばらくは違うやり方を色々試してしたい、もう少し小説よりもノンフィクションでやっていたいという動機のほうが強いですね。 ……というか、ダメなんですよ、私自身が感動型なんで、すぐ泣くしね。本を読んでいても目がウルウルしてしまい、自分の弱さがわかって恥ずかしいんです」(武田さん)
「僕の最初の本も担当は菅付さんでした。そして小説の批評をする羽目になったのも菅付さんと関係するようになったからですよ。僕はものごとを判断する軸として村上春樹という作家、好き嫌いは別として、彼を無視しないでおかなければ絶対にいまの日本の小説がわからないだろう、という場所から仕事を始めました。最初はあまり好きでもなかったのですが、彼について書けば書くほど自分なりの理解が深まり、いまはかなり読めているとは思います。それで、彼が『アンダーグラウンド』を書いたときに、つまりそれはトルーマン・カポーティにおける『冷血』と同じようなことをやりたかったと思うのだけど、僕としてはあまりうまく読めなかったのです。彼がフィクションとノンフィクションの両方で試みたことは理解したいし、武田さんもきっと意識的に彼の仕事を見てきたはずだと思うのですが、たとえば武田さんは、もし自分が小説を書いたらノンフィクション以上に世界の真実を伝えられるとか、そんなふうに思ったことはないのですか?」(仲俣さん)
「真実を伝えられるかどうかはわかりませんが、でも、たしかにフィクションとノンフィクションというふたつの軸でものを考えることは大事だと考えています。それで、ノンフィクションのおもしろさとはなにかを子細に見てみると、そのかなりの部分はフィクショナルに書き込まれた演出の部分ではないかと思うのです。ディテールの部分で、おそらく取材ではとれなかったであろう書き込みなどもあり、そういう要素が作品の魅力になっていたりもするので、その部分を禁欲的に削ってしまったときに、なにが残るのかが気になっています。ですからさっき言ったように、枠組みのなかで位置づけるとか他の分野に接続するとかいった試みが、『ノンフィクションがノンフィクションでありつつも文学的なものとは別のおもしろさで作品の魅力を放つこと』に繋がる可能性があるのかな、とは思っている。それは文学作品のように人を感動させるものではない。だけど新たな知的発見があるのだとしたら、それはフィクションの力を借りずにノンフィクションが魅力を持ったことになるのだと思います。そういう意味において、私はノンフィクションの面白さを追求しているつもりなのです。これも一例で、フィクションと対立させてノンフィクションを考えるのが自分の使命だと思っています。その観点から言うと、今のほとんどのノンフィクションはノンフィクションであろうとすると面白くないですね。事実をちゃんとした取材的方法論で拾っている限り、それは面白くなり得ないんじゃないかと思っていて、だとすれば違うところでノンフィクションの面白さを追求していくべきなのではないかと。だって、ノンフィクションの手法にこだわる限り、台詞だって取材した人の言葉をそのまま使わざるを得ないじゃないですか。相手は言葉のプロではないので、その言葉が面白いはずもないんですね」(武田さん)
「膨大な取材をこなしてきた武田さんだから指摘できることですね。村上の話に戻しますが、僕が『アンダーグラウンド』を読んで嫌だったのは、なんだか出てくる人がみんな村上春樹の小説の登場人物のようなしゃべり方をしているようでね。でも、武田さんの言うようにノンフィクションが文芸的なものから離れていくとすると、その対極には論文というものがあって、じつは学者にもけっこう面白いことを書く人がいて、武田さんも大学で教えていらっしゃいますよね。逆にアカデミックな書き方や人文書については、武田さんはどう考えていますか?」(仲俣さん)
「……その続きは、一度休憩を入れてから!」(多田)
時計は9時30分近くになっていた。休憩タイムになったものの、武田さんも仲俣さんも離席せずに話を続けている。客席前列には一般入場で参加した出版関係者や書き手も多く、この時間を利用して2人との質疑も始まった。なかでも「都市と消費とディズニーの夢 ショッピングモーライゼーションの時代」などの著者・速水健朗さんは次の予定が詰まっていたらしく、名残惜しそうに一人称やニュー・ジャーナリズムについての質問をしながら会場を後に……。いっぽう私はB&Bの担当者としてこのイベントを実現してくれた木村綾子さんを探し、時間延長は可能か訊ねてみた。「盛り上がっていますね。大丈夫ですよ」との返答を笑顔でいただき、やや安堵して再開時間を迎えることができた。
小説をインタビューの資料として読む
後半は休憩タイムでの話題も踏まえ、武田さんの研究対象のひとつであるニュー・ジャーナリズムについての論議から始まった。1960年代後半のアメリカで発生した、客観性よりも取材対象との積極的な関わりを重視した表現方法で、武田さんは「書き手として意識はしている。ベタベタの三人称物語を自分でやったことはないが、いずれこの手法をジャーナリズム的に使ってみたいとは思う」とのこと。好きな作品としてはデイヴィッド
ハルバースタムの「ベスト&ブライテスト」などジャーナリズム系のもの、また文学系ではトム・ウルフの「ライトスタッフ」などを挙げた。仲俣さんはカポーティの「冷血」について、ジェイムズ・エルロイなどを手がけた佐々田雅子さんの新訳に接し、その凄さに気づいたという。2人の会話からここまでの流れと同じように、文芸的なものから距離を置く武田さん、そして、文芸的なものの魅力の中に新しい発見をしようとする仲俣さんというスタンスの違いが伺えた。「文学や詩と縁を切った武田さんは、ではどんな作品が好きですか?」と、仲俣さんはニュー・ジャーナリズムから離れて尋ねた。武田さんの答えは「いまの私は、文学が社会現象になっていれば読む。そうでなければ読まない。だから、好きな文学はない」という徹底したもの。そのあまりの割り切りぶりに驚いてか、会場からは小さな溜息も漏れた。「待って、じゃ最後に好きだったのは?」と重ねて問うた仲俣さんに、武田さんも苦笑しながら村上春樹の初期三部作を挙げたのだが……。
「その頃まではまだ読めたのですが、以後は書評などでも文学作品に接する機会はほとんどなく、ずっとそのままですね。たとえば高村薫さんのインタビューに際して作品を読んだとしても、それは文学としてではなく資料として、作品の構造や事実関係との関連を読んでいたので、小説としては接していないです。自分がそういう構えに慣れてしまったこともあり、文学的感動には浸れないんです」(武田さん)
「さっき速水さんが帰り際に言っていましたが、僕と武田さんは、喋っていることと実質が、ほんとうは逆なのじゃないか、と。武田さんのほうが文学的な人で、僕はじつは小説を読んでも、フィクションの映画やドラマを見ても絶対に泣かない。でも、ノンフィクションは泣けるのです。映画だと、ノンフィクション系の音楽映画を観ると泣いてしまうことが多いですよ。……まあ、でも、いつか武田さんがまた文学の世界に戻ってくることもあるかもしれないので、今日はこれくらいで」(仲俣さん)
文学をめぐる談義は一段落し、話題は前半終了時に予告したジャーナリズムとアカデミズムの関係について進む。
職業的分類の意味をめぐるやりとり
武田さんは現在、大学の研究者でもある。また、自身も教員として専修大学などで学生に接している仲俣さんは、ジャーナリストでありながらアカデミズムの場にいる武田さんが、在野の出版界と大学の関係をどう捉えているかに興味を持っていた。「大学でジャーナリスティックであることは、プラスにならないのでは?」という仲俣さんの問いに、武田さんは「たしかにジャーナリストであることが大学での業績には直接繋がらないでしょう。でも私は大学にジャーナリストとしているつもりで、それは大学もまた社会との接点だからです。若い人たちと間近に接することは、毎日が取材のようなものです」と答えた。フィールドワークという意識があるのですか、という質問にも、「もちろんすぐになにかを書くというわけではないが、社会を知る場という意識は持っています」と。
「僕は学生時代、あまり学校にも行かなかったので、学問や学者に対する敬意というものを持っていませんでした。最近になってやっと、評論家やジャーナリストとは違う、学者の書くものに対する期待を含めた敬意を持つようになりましたが、でもスター学者というか、大学にいながら売れる作家も、昔からたくさんいたわけで、そのような存在について武田さんはどう思っていましたか?」(仲俣さん)
「尊敬する学者はたくさんいますが、でも、仲俣さんは分ける人だよね。私は学者とかジャーナリストを分けられない人のようで、だから大学に対しても『この人の欲望はどんなものなのか』という観点からは一般化できるので、なんでこんなことを書くのだろう、というジャーナリストへの興味と同じように、なんでこんな研究をするのだろう、という学者への興味も、職業的分類にこだわることなく同列のままで平気なのです」(武田さん)
「……なるほど。だんだん武田さんと自分の違いがわかってきました」と仲俣さんは言い、著書「<ことば>の仕事」の出版経緯について説明した。「本とコンピュータ」の編集者時代に、「共有地の開拓者たち」という連載で小熊英二氏、山形浩生氏、水越伸氏、斎藤かぐみ氏のロングインタビューをおこない、そのまま8回ぐらい続けば書籍にできるのではと、仲俣さんは思っていた。しかし企画が終わってしまったので、フリーになってから佐々木敦氏、小林弘人氏、豊﨑由美氏、恩田陸氏、堀江敏幸氏に書き下ろしインタビューを加えて本にしたものだ。自分としてはインタビューノンフィクションに挑戦したつもりでやった、と仲俣さんは振り返る。そして「いま思えば、この本では敢えてノンフィクション作家を人選しなかったのは、自分がノンフィクション作家になりたかったという潜在的な無意識の欲望があったからからかもしれない」とも。
仲俣さんの話を聞いた武田さんは、「たとえば小熊さんの仕事でも、ノンフィクションの仕事として語れる部分も多いと思いますよ」と、やはり仲俣さんの分類のしかたとは違う視点を示す。「僕はむしろ一度分類して、そのうえで越境した仕事を発見するタイプかもしれません」と仲俣さんは自分のスタンスを説明した。さらに、高村薫さんの小説を資料として読んだ、と語った武田さんのスタンスについては「僕は分けているけど、武田さんほどには距離を置かず作品に迫ろうとするのです。逆に武田さんは、肩書きや作品スタイルで分けないけれど取材対象とは一体化しないと決めているのですか」と尋ね返した。「たしかに、近くに行って一体化するとよく見えなくなる、と思ってはいますね」と武田さん。このあたりについてはスタンスの違いを確認するにとどまり、話題はインタビューや人と会って言葉を記録することへと移っていった。
吉本隆明は詩人だった
そろそろ10時になろうとしていたが、2人の対談は淀みなく続く。まさにタイトルの<“答え”が出なくても、とことん語ってみる! 〜ノンフィクションの書き手として、いま言葉にしたい幾つかの事柄>という展開。自身もインタビュー経験が豊富な仲俣さんは、武田さんに「いままで会った人のなかで、一番話を聞けてよかったと思える人と、まだ会っていないが可能なら会ってみたい人をそれぞれ1人ずつあげてください」と、もしかするとこれは仲俣さんにとって「<ことば>の仕事」番外編なのか、とも一思える質問を繰り出した。
「私は取材件数の多いライターだった時期があり、かなりの経験はしています。ただ、有名人ではなく、メーカーの商品開発に関する取材が多くて、ここで名前を挙げられるようなタイプの人はあまりいないですね。でも、たとえば新日鉄であれば『鉄は国家なり』の時代を語ってくれるような、歴史を感じるような話が聞け、そういうときにはよかったなぁと思いました。ただ私は取材に関しては人を書くのは自分の仕事じゃないと思っているのです。時代や社会を書くことが自分の仕事で、人を描くことを最終目的地にはしていない。そうであるが故に、インタビューで話を聞いたとしても、そのままは書きません。その話がどういう文脈で言われていたか、この話はどういう社会のなかで語られたことなのか、そこを自分なりに明確にして書くのが私の仕事だと思っています。人に聞いて何かものがわかるとも思えないところがあり……、いや、相手の言葉を信じないのではなく、そもそも言葉そのものが語れることはあまり多くはないと考えています。その言葉が社会のなかでどういう関係性を持っているか、とか、そういうことまで含めてコメントしてくれたことを分析すればわかる部分は多いと思いますが、言葉そのものと自分という存在を向き合わせてみて、そこでなにかがわかるかというと、そういうものではないと思うのです。人から言葉を聞いて、そのあとで1回外に出てみないと使いものにはならないと思っているので、インタビューは私にとって辛いものでもあります。もちろんそこに重きは置きつつも、1回は外れたい、外に出ることでインタビューを活かしたいという気持ちがあるのです。だからオーラルヒストリーも、たんに聞くのではなく、その後の分析のほうに私は興味があります」(武田さん)
「私は正直に言うと、いままで数多くのインタビューをしてきていますが、じつは苦手です。できたら本だけを読んで本だけを批評したいのだけど、でもなんでこんなふうに思うのかというと、僕のところにはいわゆる普通のインタビュー、雑誌から求められるO&A形式の、読み物的な、要請された形式のものが多いからだなのじゃないか、と。それと、聞いた話を書くことはあまり問題がないのですが、その前に人に会うのが怖い、たとえば著書を1冊も読まずに会うのは失礼だと思うけど、でも著書を10冊、20冊読んだら仕事はまったくお金にならなくなるし、そもそも本当に好きな人に会うのは、すごく緊張しちゃうんですよね」(仲俣さん)
インタビュー体験を語るなかで、仲俣さんは吉本隆明氏を取材した際の逸話を披露した。2011年、自身の父親が逝去された直後のことだ(その詳細ついては一部が「ウィッチンケア第3号」掲載の「父という謎」という作品でも触れられている)。「僕にとっての、会ってほんとうによかった人だった」と仲俣さん。仲俣さんは吉本氏の娘・よしもとばなな氏と同い年であり、「自分の親世代で、面倒くさいと思いつつも影響を受け、距離を置きたいと思っていた人物」であった。しかし父親のこともあり、いま会っておかなければという気持ちで取材を引き受けた。「記事自体は普通のインタビューとして掲載されましたが、そのときの吉本氏の印象、書かなかったことのほうが忘れられません」と率直に語る。雑誌のライターとしての不自由さを感じ、もし自分がノンフィクション作家であれば別の書き方ができたかもしれないという意識があらためて募った体験だったという。その話を聞いた武田さんは「そこは勇気とテクニックで、なんとか商品として落とし込む方法を見つけるべきだったのかもしれない」とアドバイスをし、関連して自身の吉本隆明観についても語った。
「私も会いたかったですが、けっきょく機会がなくて残念でした。若い頃、知り合いのちょっと上の世代にすごく吉本を好きな人がいて、『共同幻想論』を聖書のように読んでいました。私はその神話化された雰囲気がすごく嫌いで、彼に対して反感を持っていた時期もあったのです。その後、自分でも文書を書くようになり、『早稲田文學』をやっていた頃の重松清さんが対談をセットしてくれたこともありましたが、そんな経緯があり会うことをびびって嫌だなと思っていたら話が流れてしまい、けっきょく日野啓三さんに会わせてくれて、私は日野さんが好きだったからそれはとても嬉しい体験でした。でもその後『偽満州国論』を書いたときに吉本氏のことを批判的に書いて、私は田川建三のシャープな吉本批判のほうが間違いなく正しいと考えている人間ですが、それでもいまになってみると、吉本隆明を詩人として捉えればすべてが許せてしまう。『共同幻想論』も詩的な作品だと思って読めば、私が若いことにあんなに嫌だと思ったのに、いい詩だなと思えてきて、そうなった後には会いたかったなと思うのです」(武田さん)
「僕もまったく同じ印象でして、ある意味佐野眞一さんを小説家、物語作家だと思うように、吉本さんを詩人だと思って触れれば、優れた作品だなと思えるのです。そんな思いで会いにいった吉本さんは宮沢賢治と夏目漱石の話ばかりしていました。そして書斎を撮影させてもらう際に漱石の写真が飾ってあるのを見て、まるでジョン・レノンの写真を飾る中学生のような人だな、と思いました。吉本さんのことについてはいつか僕も新たに書こうと思っています」(仲俣さん)
吉本氏にまつわる話の最後に、仲俣さんはもう一度「武田さんが今後会いたい人は?」と尋ねた。武田さんの答えは「うーん。鈴木慶一かな、ムーンライダーズの。一緒にごはんを食べたことはあるけど、インタビューしたことはないんです」。時計は10時半に近づいていたが、まさか、3.11を議題に始まった2人の対談が、音楽にまで及ぶとは!
フリージャズ、プログレ世代とパンク世代
武田さんはどんな音楽をやっていたのですか、という仲俣さんの問いを受けて、武田さんは自身の音楽変遷を語る。
「高校の頃にはフォークやロックをやり、その後は基本的に頭でっかちなほうなのでどんどん難解なものへと向かいました。大学時代はフリージャズやパフォーマンス、それも極めちゃって1回終わりに。まあ、放っておくとジョン・ケージの『4分33秒』にいっちゃうような、そんなタイプでしたから、なにもやらないことが音楽だ、みたいになって、もうやることがない状態でしたね。社会人になって再開した時はスティック・タッチボード(チャップマン・スティック)という楽器をイギリスで家内が買ってきてくれて、いまはみんな両手でギターを弾くようになりましたが、当時は珍しいし難しくて、それと格闘しながらライヴをやったりしました」(武田さん)
「僕は出版関係での仕事の最初が『シティロード』での音楽編集者でしたから、20代は朝からレコードを聞いてコンサートにいって編集して、という生活が3年ぐらいありました。資質ではなく世代の違いでいうと、武田さんはジャズやプログレもかじっただろうし、基本的に難しい音楽、頭でっかちで演奏テクニックもけっこう必要な音楽の影響を受け、だけど楽器ができちゃった人だと思うんです。それで僕らの世代は基本的にパンク以降ですので、まあギターは弾けて、スリーフィンガーなんかもできるんだけど、でもたとえば優等生がパンクをやって自分の優等生時代を否定するような、そんな音楽が主流でしたね。まさにバンドブームの世代です」(仲俣さん)
「たしかに難しさを誇る、みないなところはありましたね。随分熱心に私も練習もしましたが、それでも、プログレを例にすればイエスやキング・クリムゾンは難しすぎてできなかったですよ。ピンク・フロイドは個々に弾いているフレーズはそれほどでもないけど、雰囲気を出すのが難しい」(武田さん)
音楽の話になると、2人の会話は互いの持論をぶつけるというより、男子同士の教室や喫茶店でのお喋りのようになった。「ノンフィクション作家とかジャーナリストとか編集者とか文芸評論家とかって、一般的には色気がない、散文のなかでももっとも水気のない仕事に就いているわけですけれど、でも実際には音楽や芸術というウェットなものに触れたりしている」と仲俣さんは自嘲気味に言ったが、ご両人が公的な仕事で制御しているその部分、その「消化(昇華でも合っているような気がする)の方法論」にこそ、私は魅力を感じているのだと思った。
仲俣さんに初めて原稿依頼をしたとき、私は「なにか他では書いていないような、おセンチな作品をお願いします」と言ったことを思い出す。そして音楽話に乗じてもう少し個人的な雑感を書けば、武田さんの「ものを書く方法論」で思い出したのは、ベーシストとして高い技術を持つ細野晴臣がYMO結成時、他の2人に見せたグループのコンセプトメモのことだ。そこには「マーティン・デニーの『ファイアー・クラッカー』をシンセサイザーを使用したエレクトリック・チャンキー・ディスコとしてアレンジし、シングルを世界で400万枚売る」と書いてあったという。詩や文学を封印して言葉を紡ぐ武田さんのやり方は、エモーショナルな演奏テクニックを封印して電子音で人を踊らせようと考えた細野氏の発想と似ているように感じられる。
あらためて、書くという仕事について
長い対談の最後に、仲俣さんはもう一度「書くという仕事」についての武田さんの思いを尋ねる。「僕はいい仕事だと思っています。次々と対象を変えていけるし、自分の年齢や成長に合わせて媒体を変えていけるというのも、得難い仕事だと思います。いかに型にはまるかを経験値として測ることが多い社会ですが、この仕事は、もちろん人間的な成長としては持続性があるのだろうけれど、前の経験をとりあえずゼロにして次のテーマなり、仕事のスタイルなりを選べるので、そうした仕事ぶりが合っている人にはぜひ言い書き手になって欲しいと思います。ただ経済状況としてたいへんになってきているので、そこは問題でしょうけれど」と武田さん。
それを受けた仲俣さんは、とくに若い人を意識して、これからライターになろうと思う人はどうすればいいのかと、2007年に「『丸山眞男』をひっぱたきたい——31歳、フリーター。希望は、戦争。」で論壇を揺るがせた赤木智弘氏の名前も出し武田さんに意見を求めた。どうやらお二人とも赤木氏とは知り合いのようで、武田さんの対談での発言によると、出会いは「赤木君がネットで私を批判する文章を書いていて、それをエゴサーチで見つけて反論したら素直に意見を聞いてくれて会話が始まった」そうだ。
さらに書き手としての心得についての話は続き、最後に「これからのノンフィクションの書き手として、日々どう生きればいいんでしょうか? 今日はお金の話を全然していませんし」と仲俣さんが自虐的に質問すると、参加者(同業者率高し)からも笑い声が響いた。
「やりたいようにやればいいし、なるようにしかならないって。いまはアクセスのしやすさで情報過多に思えるかもしれませんが、私はメディアの風景が変わっただけで、本質は変わっていないと思いますよ。昔だってたくさんのものを読まなければいけないという強迫意識はあったわけだし。だから私は、数多く読んだからいい仕事ができると思う必要はないと思います。むしろいままでやってこなかった方法から新しいものが生まれる可能性を信じたほうがいい、と。過去に失敗した方法は失敗しか生まないので、押しつぶされるよりは、いままでと違う考え方をするべきだと思います。ただアウトプットのメディアが分散したので、いまは相対的に原稿料も安くなっているしたいへんですよね。僕が書き手として働き始めた頃はバブル期の最後で媒体も多く、自分から売り込みをしなくても駆け出しから原稿料で生活ができていました。それは恵まれていたと思います」(武田さん)
「メディアの風景が変わって見えるだけ、というのは武田さんらしい意見だし、実はそうなのだと僕も思います。そしてもうひとつ語弊を恐れずに言えば、僕は『ほんとうに才能がある』というか、面白いもの書きがいて、すでに書き上げた原稿があったとすれば、それを何人かの編集者に見せて価値がわからないということは、たぶんないだろうと思っています。いや、ほんとうに理解できないくらいすごくて早過ぎちゃったら無理かもしれないけれど、でも見出せない才能はないんじゃないかと。……ただ、才能は自分ではわからないというのが最大の問題だから、そこはしょうがないのですが、他人に委ねるという勇気があれば、食べていけるかどうかは別にして、見出されないということはないのではないか、と。そうは言っても僕は49歳だし、武田さんも50代半ばで、ある種の既得権で生きているので、必ずしも若い世代にとっては納得のいく話しではないかと思います。ですので、せっかくですから、若い人でもそうでなくても、これまでの話に文句、不満、抗議など言いたいことのある人は遠慮なくどうぞ」(仲俣さん)
10時半を越えて質疑応答になったこともあってか、異議申し立ての声は上がらなかった。やや先を急ぐ展開でもあり、仲俣さんが「僭越ながら逆指名のかたちで進みます」と断りを入れ、3名の来場者に感想を求めた。
1人目は『「フクシマ」論』などの著書がある開沼博さん。書き手と読者の一体感に対して自分は抗えるのか、との思いを武田さん仲俣さんと語り合った。「本ができあがると、すぐ間違いに気づいて投げ捨てて次の本を書きたくなる。自分はそんな性質なので相手が一体感を持ってくれても、その時点で自分は既にごめん被りたくなる心理状態です。そこにもしかしたらヒントがあって、自分の間違いに気づけることこそが一体感に抗うことなのではないか」という武田さんの言葉が印象的だった。2人目は「僕の見た『大日本帝国』」などの著者・西牟田靖さん。7年越しで書き続けている本の終わらせ方、ノンフィクション作家と呼ばれることについてが話題だった。そして3人目は「Get
back, SUB!」の著者・北沢夏音さん。文芸とノンフィクションの関係をより豊かに、と提案し2人と話し合った。「ノンフィクション作品は既存の文芸誌にもっと浸食していくべき」という仲俣さんの提言は刺激的だった。
北沢さんとの論議の流れで、武田さんはもう一度方法論について言及した。
「書くための方法論に自覚的でいたいというのは、たとえば写真であれば、これは35ミリで撮ろう、これはブローニーだなどと内容や使用目的に応じて形式を選ぶでしょう。でも文字の人はそういう発想はしないですよね。私はそれがすごく貧しいと思っていて、適正な形式を選ぶことがあれば、文字の表現はさらに豊かになれると期待しているのです。写真家の表現と比較して、文字がそれと同じようなことができているのかとつねに問うてみたい。そんな思いもあって、今日は方法論について自覚的でありたいという話をしました」(武田さん)
「方法論がわからないと印象批評になってしまいますよね。小説に対する印象批評は、それはそれで芸になっている部分もありますが、ノンフィクション作品がどういう方法論で書かれているか見抜けない場合は、ほんとうに先ほどの話のようにエモーショナルな共感か反発しか生まない。そしてその視点については、僕も書き手としてではなく読者としてまだ全然レッスンしていないと、今日の話で気づきました。だからこれが武田さんの新しい仕事の軸となり、いつかまとまったものとして読んでみたいと思いました」(仲俣さん)
約3時間の対談が終わっても、武田さんと仲俣さんの周囲には人が集まり、歓談の熱気はなかなか冷めなかった。各自が“答え”を見つけるためのヒントになる、種のような言葉が撒かれた金曜日の夜。レポート書いてみた私も終わらせ方がわからぬ、というのが正直な感想。ここに記録した文字がきっかけ(媒介)で、いつかどこかでだれかがなにかを考えたり感じたりしてくだされば、私は嬉しく存じます!