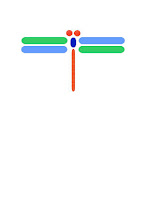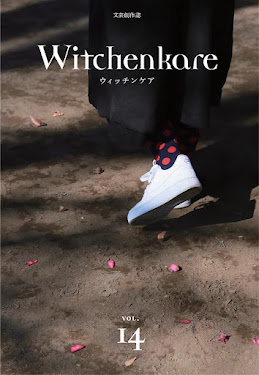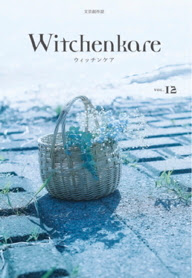昨年12月に武田徹さんが上梓した「ずばり東京2020」は、朝日新聞社の言論サイト「論座」で2018年8月から連載したルポルタージュに、新たな「東京コロナ禍日記」を書き下ろした1冊。タイトルからもわかるように、当初は前回の東京五輪を題材に開高健が書いた「ずばり東京」の2020年度版としてスタートさせたものの、諸般の経緯で奇しくもノンフィクション同時代史に...ええと、本日(5/11)も五輪の行方は五里霧中と言ってもいいのかな。ニュースには「さざ波」「絆」といった言葉が殺伐と飛び交っています。でっ、この先どうなるのか私にもまったくわかりませんが、しかし一昨年の10月半ばごろ、当初東京で開催予定だったマラソンがよくわからない経緯で札幌に変更されたことをどうしても思い出してしまうし、そういえば2002年FIFAワールドカップの日韓共催のころにも、この国では同じような空気が流れていたなぁ。つい最近、武田さんはクローズドなSNSで未来を予測するようなことを書いていて...うん、私もそんなふうにものごとが進みそうだと感じています。
武田さんの小誌今号への寄稿作は〈日本語の曖昧さと「無私」の言葉〉。第2号に掲載した〈終わりから始まりまで。〉から一貫して、「言葉」をテーマにした考察を試みてくださっています。今回、前半部の事例として挙げられている〝9時10分前〟ですが、もちろん私は「それは8時50分のことでしょう」と疑いすらしなかったです。「世の無常と非情」という一節、他人事とは思えず。そして作品後半では、記者経験がある哲学者・森本哲郎の〝新聞記者になって、僕がいちばん苦労したのは、文章から「私」を抹殺するという訓練だった〟で始まる一文も引用しつつ、「ジャーナリズムが自分たちの使っている言葉のあり方それ自体について意識的になること」の大切さを語っています。引用文内の〝文章から「私」を抹殺〟...これ、すごくわかりまして、自身の経験でも「私」とか「ボク」とか「俺」なしであるグレードの文章を仕上げるのって、ちょっとコツをつかまないとしんどいんですよ。ときどき「〜だと●●●は思う」みたいなので、●●●部分が雑誌名とかの原稿に出くわすと、ああ、苦肉の表現だな、と思ったり。
反動、なのか? ウィッチンケアをつくるようになってから、このような場所で寄稿者の作品を紹介するさいにも、つい「自分のこと」として語る悪いクセが付いているかもしれません、私。ですので、みなさまにおかれましては、ぜひ武田徹さんの寄稿作をダイレクトにお読みいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
実はジャーナリズムは人工的に日本語を変えて来た前例がある。たとえば記者がエッセーを書く場合を除いて記事を語る主語(=「私」などの一人称)を書かずに済ませようとする。取材して手に入れた事実を、事実そのものが語るような文体で書こうとするのだ。記者の主観を逃れて記事の客観性を確保するための修辞技法だが、これは日常的な日本語表現にはありえない特殊な記述法だ。
〜ウィッチンケア第11号〈日本語の曖昧さと「無私」の言葉〉(P068〜P073)より引用〜
武田徹さん小誌バックナンバー掲載作品:〈終わりから始まりまで。〉(第2号)/〈お茶ノ水と前衛〉(第3号)/〈木蓮の花〉(第4号)/〈カメラ人類の誕生〉(第5号)/〈『末期の眼』から生まれる言葉〉(第6号&《note版ウィッチンケア文庫》〉/〈「寄る辺なさ」の確認〉(第7号)/〈宇多田ヒカルと日本語リズム〉(第8号)/〈『共同幻想論』がdisったもの〉(第9号)〈詩の言葉──「在ること」〉(第10号)
【最新の媒体概要が下記URLにて確認できます】
【BNも含めアマゾンにて発売中!】