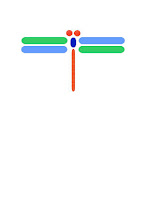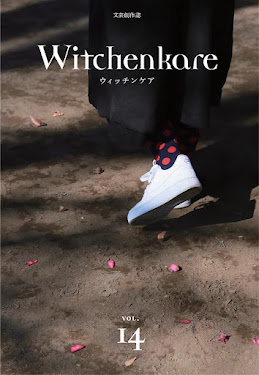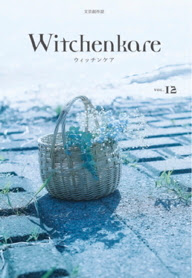本誌レギュラー寄稿者のひとりでもある、編集発行人の多田洋一さん。そんな彼がウィッチンケア第13号に寄せた「パイドパイパーハウスとトニーバンクス」は、ご自身の記憶に刻まれた過去の経験や知見をもとにした音楽エッセイ……かと思いきや、当人はこれを「小説です」とおっしゃる。ううむ……。そもそも〝何について書かれた〟文章なのかから紐解いてゆきましょう。まずはタイトルに並列された2つの固有名詞について。
▶︎「パイドパイパーハウス」は、1975年から1989年まで、東京都港区南青山の骨董通り沿いにあった、主にアメリカのウェストコースト・ロックやAORなどを取り扱っていた輸入レコード店。
▶︎「トニー・バンクス」は、1950年生まれ/イングランド出身のロック・ミュージシャン&鍵盤奏者。1970年代、シアトリカルかつシンフォニックなプログレッシブ・ロックで人気を博したバンド「ジェネシス」の創設メンバーのひとり。
これらの〝手がかり〟を一瞥しただけで「よくわからない」「自分には関係なさそう」と思われる読者もいらっしゃるかもしれません。とはいえ、この〝2つ〟の話に終始するわけでもありません。他にも「渋谷のHMV」とか「外道」や「裸のラリーズ」(いずれも約50年前に活躍した日本の伝説的ロックバンド)とか……いや、ますます引かれちゃう?
テキストの約4分の1は「ジェネシス」のバンド・ヒストリーを(同グループの裏リーダー的存在である)トニー・バンクス=TBを基点に振り返ったもの。バンド以外のソロ活動に足を踏み出して以降、多くの構成員が、バンド本体とはまた別に、華々しい成功をなしとげたなか、なぜかTBその人だけが〝ぱっとしなかった〟という史実。しかして総勢10名を超える歴代メンバーのうち、文中でTB以外にフルネームで呼ばれるのは、たった2名が1度ずつ。では(それらの例外を除き)原稿内で各メンバーがどのように呼ばれているのかというと、「同級生、下級生、学外のメンバー、役者経験のある男、ロンドン出身の男、若い男」等々。ついでに「ジェネシス」の作品名=アルバム・タイトルに目を向けても(『Selling England by the Pound』と『...And Then There Were Three...』の2枚だけ例外として)「二枚目、三枚目〜第十五作目」とリリース順の通し番号が振られた、そっけない記述。しかし、これらを(わかりやすくて意味が通りやすい)具体名や正式タイトルで綴ったのでは、それこそ音楽エッセイと大差ない。あくまでも本作が「小説」として綴られた心情を解きあかす鍵は、どうやらそのあたりにありそうです。
……と、ここまでTB関連記述の説明に終始しましたが、じつは本作の〝核心〟にあるのは、もう一方のキーワード「パイドパイパーハウス」に象徴される「かつて僕の居場所であったレコード屋がほとんどの町からなくなってしまい、あらためて痛感したこと(本作より引用)」だったりするのです。当紹介文を綴っている自分は、多田さんとは三歳違いでほぼ同世代であり、「レコ屋が居場所だ」という感覚も十二分に賛同できるのですが、そういう基盤を持たない方々にとって、一連のトピックや心情がどう映るのか、そこは逆に興味津々なところでもあります。
「お出かけの理由」であり「旅先でのミッション」であり、ひいては「働くこと〜生きていく方便〜生きる糧」だったレコ屋巡り。実質上、それらが叶わなくなった令和の世において、主人公が達した(悟りにも似た)境地。それは、音楽にそこまで思い入れのない方々にとっても──たとえば街中の書店や古本屋だったり、まんが専門店、ゲーセン、プリクラショップ、お気に入りの名画座、ミニシアター、町中華、喫茶店、おもちゃ屋、駄菓子屋──そうした特定の(文化にまつわる)〝場〟をめぐる郷愁や執着などとも代替可能なのかもしれず。多田さんが誘う「ありし日の音楽経験」に根ざした掌編小説、ぜひご堪能ください。
[文:木村重樹]
物心ついたらレコード屋、恋愛を知ってレコード屋、家庭を持ってもレコード屋、リタイアするまでレコード屋──と、どうやら人生のこのへんでレコード屋自体がほぼ消滅状態になっちゃうってことを想定できてなかったわけだな、この人は──黄泉の国でもレコード屋。やっぱり、糞だな。
喪失感に浸って挫けるくらいなら、僕のお薦めは〝書き換え〞です。
〜ウィッチンケア第13号掲載「パイドパイパーハウスとトニーバンクス」より引用〜