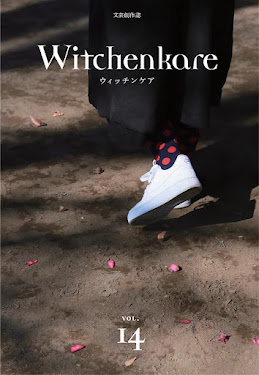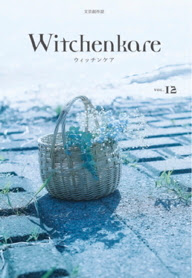武田徹さんの今号寄稿作は、今年1月に上梓された「日本語とジャーナリズム」の冒頭に登場する荒木亨先生(大学博士課程時代の指導教官)との、〝もうひとつの逸話〟ともいえるテーマを扱っています。私は今年1月に荻窪の書店「Title」でおこなわれた武田さんと柳瀬博一さんの対談に伺いましたが、その際にも荒木先生にまつわる話は少なくなく語られていました。今作には<筆者は先生から影響を強く受けたが、師弟関係は喧嘩別れという不幸な結果に終わった>という、読者が一瞬ひやりとさせられる一節もあるのですが、しかし読み進めるに従い、武田さんが師の教えを尊敬の念で受け継ぎ、時を経てご自身の課題として展開していることが伝わってきます。
荒木先生の仕事のひとつに日本語のリズム論があり、著書によると<日本語の音節は等時的拍音形式、つまりどの音節もほぼ同じ長さで使われる>...私は今回、武田さんの文章を読みながら声を出したり(歌ったり)、デスクを指先で叩いたり。目で文字を追っているだけではピンとこないことが、耳や皮膚も経由させると「なるほど!」と腑に落ちるのです。なんか、ストレッチのやりかたを書いた文を読んで実際に身体を動かしたら「おー、たしかにこれは効く」、みたいな体験をしました。
作品半ば以降は、荒木先生の日本語リズム論を踏まえたうえで、たとえば宇多田ヒカル「Automatic」などを事例として、「歌の日本語」が考察されています。武田さんは宇多田のデビュー時、<冒頭の「七回目のベルで」は〈休ナ・ナ・カイ・メノ/休べ・ル・デ……〉と分節されるように感じられ>て、<従来とは異なる日本語の使い方が登場した>とエッセーで指摘したこともあった、と。...部分的な引用ではうまく説明できませんのでぜひみなさま、小誌を手にとって、目以外も動かしながら本作を読んでみてください!
終盤では「歌の日本語」に対する、ジャーナリスティックな考察へと拡がっています。これまでの小誌掲載作でも「詩」の言葉(日本語)について、注意深く読み解いてくださっている、武田さんらしい視点、そして示唆に富む指摘。音楽好きな私も、ときどき<「歌」が作り上げる共同性>については「おや!?」と感じた記憶もあるので...うまく表現できませんが「それに持っていかれちゃわない」心構えもどこかに有して、「歌の日本語」に接したいと思いました。
たとえば本誌前号で取り上げた「日本語のロック論争」の担い手の一人・松本隆は「愛餓を」という日本語をテーマにした戯歌の歌詞を書いているが、大滝詠一に歌われた時それは〈アイ・ウエ・オ休/カキ・クケ・ココ・ココ/サシ・スス・セソソ〉と二拍子の5・7調になって、荒木説に従っている。このように70年代の日本語のロックは荒木説で説明できる日本語のリズムの支配を受けていたが、90年代になるとメロディー優先で日本語のリズムを裏切る歌を許容するように変わったのだろうと筆者は考えた。
だが、その仮説はあっけなく覆される。宇多田ヒカルのデビューと前後して刊行された佐藤良明『J-POP進化論』には〈休マ/ケエ・テ・クヤ・シイ〉で始まる「花一匁目」のように休符から始まる歌が日本には古くからあることが示されていた。
ウィッチンケア第8号「宇多田ヒカルと日本語リズム」(P076〜P081)より引用
https://goo.gl/kzPJpT
武田徹さん小誌バックナンバー掲載作品
「終わりから始まりまで。」(第2号)/「お茶ノ水と前衛」(第3号)/「木蓮の花」(第4号)/「カメラ人類の誕生」(第5号)/<『末期の眼』から生まれる言葉>(第6号)/<「寄る辺なさ」の確認>(第7号)
http://amzn.to/1BeVT7Y
Vol.15 Coming! 20250401
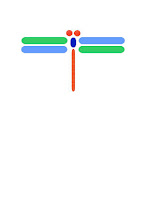
- yoichijerry
- yoichijerryは当ブログ主宰者(個人)がなにかおもしろそうなことをやってみるときの屋号みたいなものです。 http://www.facebook.com/Witchenkare