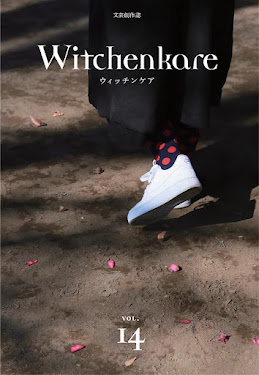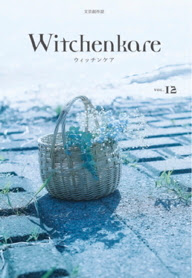「《辺境》の記憶」の寄稿者・東間嶺さんとは、第4号寄稿者・橋本浩さんを介して知り合いました。東間さんはウェブ・オピニオン空間「En-Soph」の編集管理人。ネット上でも積極的に発言していますが、じつは私は、東間さんが「言論の箸休め」的にアップする料理関連のツイートとか、けっこうファン。同年代の寄稿者・辻本力さんとどっちの料理ショー(古!)みたいなことやったら、すごい高レベルだと思います。
東間さんは作品内で「決定的な経験」として<自分が世界を表現するに足る特別な《メディウム/媒介》として、《ことば》という手段をはっきりと意識化、対象化し得たということ>と書き表していまして、なかなかスタイリッシュな文体なのですが、これはざっくり言い換えると「オレのブルースはやっぱりストーンズでギター弾くことなのさ、ロックンロール!」(By キース・リチャーズ/もちろん私の創作発言)、みたいなニュアンスなのでしょうか。。。
そして作品の冒頭に登場する<書き終えられた二万七千字弱の小説>...これは戸籍名義で「多摩美文學」(青野聡教授退官記念号/2014年3月20日発行)に納められた「≠ ストーリーズ」という作品。小誌掲載作と併せ読むと、東間さんの《ことば》や文章、そして「書くこと」への繊細な意識がより伝わってきます。1957年のハバナを舞台に始まる《〈史実〉ではない革命をめぐるクライム・ノヴェル》はめぐりめぐって新宿の喫茶室ルノアールや金井美恵子の皮肉へと回収...いや全然回収はされていないか...でもこの物語が断念されなければ、<きっと、そう、そういうことだ>と最後につぶやいた男もまた、さらにメタな物語の一部になっていくのかな? 作品内に登場した「文学的浣腸(仮)」という言葉が、妙に心に残りました。
《ことば》についてはそれほどむかしでもないむかしに「ちぇっ」と思ったことがあってそれは「ものごころつくまえに自分で言語が選べたらよかったのに」ということででもそれはべつに「英語が選べたらもっと国際人になれたのに」みたいな意味ではなく、私(←とりあえず便宜上)が私について書いたり喋ったりするさいにはすでに借り物である「私」かそのバリエーションである「僕」「オレ」「あっし」などしか選択肢がないとあらためて気づいたということで...まあ人間はいつどこで生まれて死ぬかも自分で選べないからそれでがんばるしかないんですが(このへんのことはきちんと書物になっていて、きっと私が知らないだけ)。
それはちょうど院生になった時期で、まずまずの手応えとそれなりの成績評価を得た卒業制作を元にしたギャラリー展示も決まっていたのだけど、同時に、それまでの在学中、しばしば指導教官たちからの講評で「作品より、きみ自身の考えとか発言とかふるまいの方が面白いよね」とか「言ってること、考えてることと、実際作ってるものとのあいだにズレというか、距離があるという印象なんだよね」などと、「要するにお前の作品ってなんかつまらないよね」と言われていたことの内容が、どうもかなりクリティカルな指摘なのではないか、と自分でも薄々思いはじめていた時期でもあった。
当時のわたしは鉄や木や皮布の箱に入った手のひらサイズのミニチュア絵画を、当時の恋人(多摩美生)の献身とやりがいと労働力を吸い取りながら二人でせっせと作っていたのだけど、そうやってアウトプットした《もの》と自分とのあいだに横たわる違和感というか、不自然さみたいなものはだんだんと増すばかりだった。作った《もの》に対して、どうしても言葉を費やすことを止められない。これはああでこうで、こうでああなんですよ、というエクスキューズがどうしても止められない。なら、最初から、これはああでこうで、こうでああなんですよ、と言うだけでオッケーなのではないか?
そんなとき思い立ってゼミへと参加し、《ことば》だけを対象化した《ことば》が飛び交う空間で、《ことば》によって自分を語り、世界を描き、彫塑し、物語することへ次第に熱中していった結果、二年経って院を出るころには鉄や木や皮布の箱に入ったミニチェアたちはアトリエの隅で冷温停止状態に置かれ、わたしは代わりにせっせと楽しく小説を書くようになっており、さらにゼミの発行する冊子の編集責任者までしていて、ついでに恋人からは縁を切られていた。
ウィッチンケア第5号「《辺境》の記憶」(P218〜P223)より引用
http://yoichijerry.tumblr.com/post/80146586204/witchenkare-5-2014-4-1
Vol.15 Coming! 20250401
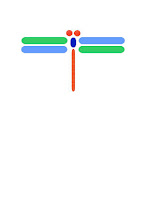
- yoichijerry
- yoichijerryは当ブログ主宰者(個人)がなにかおもしろそうなことをやってみるときの屋号みたいなものです。 http://www.facebook.com/Witchenkare