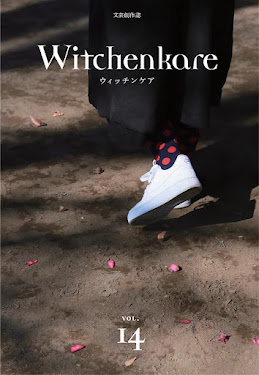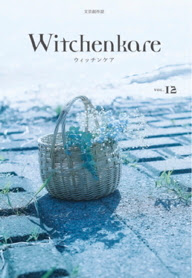我妻俊樹さんとは廻ってないお寿司(ランチ)を食べながら打ち合わせをしました。
小説を書き、小説について考え、短歌を詠み、短歌について考える...我妻さんのネット上の言葉を追っていると、ある意味ですごく規則正しい生活態度であるなぁ、と感銘を受け、こちらの背筋もしゃきっとします。いや、もちろんさまざまな雑記にはそのふたつ以外のあれこれも登場するのですが、しかし、本筋はびしっと「書くこと」で貫かれている、という印象を受けます。
お寿司を食べた後の、「珈琲の殿堂」(純喫茶!)でのこと。話の流れで私が「今号ではエロいノワールを書こうと思って...」と言ったら、なぜか我妻さんの笑いのツボに入ったみたいで...いやあ、我妻さんってあんなに無邪気に笑い転げることもあるのかぁ、青春スターのような爽やかな笑顔でした!
原稿を媒介にした我妻さんとのやりとり(メールと電話)でのニュアンスが、私にはとてもおもしろかったです。「作品=ただ文字が並んでいるもの」に対する、書いた人と読んだ人(しかも光栄なことに最初の読者だ!)の視座のちがいというか...ええと、わかりやすくたとえますと、たとえばトマトを育てた人は「丸くて赤いトマト」だと思っていたのかもしれないのだけれど、そのトマトを食べる人は「緑色の蔕が鮮やかなトマト」だと思っているかもしれないという...って、全然わかりやすくないじゃん! もう少し作品に即して書きますと、私は原稿を受けとって数度読み、頭のなかで一番ひらひらしていたのが白布だったのです、物語内の語り部がまとった、白い布。でも我妻さんが書き進めながらピントを合わせようとしていたのは、そっちじゃなかったような印象があるなぁ(推測)。むしろその白布男が語っている、地理的なことというか、移動に関することというか...。あっ、私の解釈なんてどうでもいいですね、読者のみなさまには(引っ込みま〜す!)。
我妻さんが寄稿してくれた「腐葉土の底」については、ご自身がブログで言及しています。「去年の後半くらいから考えてきた小説についてのいろいろなことの一部が、少なくとも具体的なひとつの形にはできたという作品にはなっていると思います。」との一文には、発行人としてぐっときたなぁ...そういうものを発表する場としてWitchenkare vol.2が機能したのであれば、まっこと嬉しいでありまする!
すべてあえかな寝言のたぐいだったのかもしれない。それでもいくばくか苦い真実がそこに含まれていたのはたしかだろう。ゆるんで肩に垂れたぼろ布からは煙草のきつい匂いがひろがった。まぶたを閉じたまま、杯を器用に戻した右手でテーブルにほおづえをついた。布がたわんで鰐のような口があらわになる。細い歯の隙間から見える口腔が血を吐いたように赤かった。
「首になってしばらくは貯金と両親の家を売って食いつないでいたものだ」
突然男は話を再開した。まわりにはとうにだれもいなくなっていたので、声は独り言のように張りをうしなっていた。ボタンのとれかけた袖口から菜箸でつまんだ蟹のように手首がのびて、床をせわしなくまさぐっている。
「おれは墓県を出ることを決意した。生まれてから一度もよその土地の味を知らないので、まずは想像することからはじめたものだ。峠を越えるひどく急峻な鉄の階段が、アパートの廊下のつきあたりからはじまっていた。そんなことは今まで考えてもみなかったが、おれの住居は県境の山脈に半分埋めこまれるように建っていた。山の中心に沸騰する温泉の音がモーターのように床を震わせ、思えば、夢の中でもたえまなくひびいていたものだ。階段は軽快な足音をたてておれの体をはるかな頂上めがけて跳ね上げていった。途中思いがけないところに部屋の窓が光っていた。二階建てとばかり思いこんでいたボロアパートだったが、山肌がめりこむように二階より上を目隠ししていただけらしい。崖にせりだした緑色の岩にはさまれたガラス越しに女の暗い顔がこっちを見ていた。頭に帽子のように大きな貝殻をのせていたので、部屋がうすよごれた水槽のように感じられたものだ。ユーカリの大木の下にささやかな広場があり、タクシーが一台木陰に乗り捨てられているのを見た。しばし休憩をとるつもりでほこりっぽい座席にすべりこむと、そのままおれはぐっすり眠ってしまった。気がつけばタクシーは夕闇の中をぶるぶる揺れながら疾走していた。運転席には大柄な狒々が座っていて、カーラジオから聞いたことのない外国の政変のニュースが流れていた。その国の名をあれから二十年間一度も思い出したことがない。思い出しそうになると鏡とナイフをこすり合わせた音が大音量で聞こえてきて、鼻の奥で山羊の髭を燃やした匂いがする。やがて夕日の光が絶えると急停車し、狒々はおれを力ずくで引きずり出して道端へ放り投げた。みごとな腕力だったよ、そして何の迷いもなかった。まわりには錆びてくずれ落ちた鉄階段の跡がころがっていた。何かに踏み潰されたものみたいに痛々しく見えた。ああいう光景が物事の境界線にはいやというほど散らばっているね、じっくり観察しようとすれば、心はおのれ自身を見うしなう。今まで走っていたはずのくねくねした道は、テールランプに照らされながら蛇のように巻き取られていくところだった。
〜「Witchenkare vol.2」P110〜111より引用〜
Vol.15 Coming! 20250401
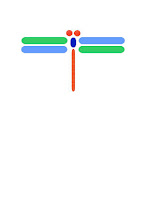
- yoichijerry
- yoichijerryは当ブログ主宰者(個人)がなにかおもしろそうなことをやってみるときの屋号みたいなものです。 http://www.facebook.com/Witchenkare