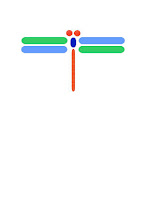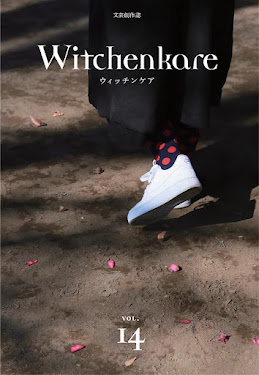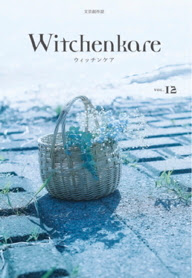Witchenkare vol.6
Witchenkare vol.6発行日:2015年4月1日
出版者(not社):yoichijerry(よいちじぇりー)
ISBN:978-4865380309
本体:1000円+税
http://www.facebook.com/Witchenkare
https://twitter.com/Witchenkare
“寄稿者37名の書き下ろし作品を掲載した文芸創作誌”
※各作品名をクリックすると「一部立ち読み」ができます!
CONTENTS
002……【目次】
004……仲俣暁生/1985年のセンチメンタル・ジャーニー
008……西森路代/壁ドンの形骸と本質
014……開沼 博/ゼロ年代に見てきた風景 パート2
020……姫乃たま/21才
026……武田砂鉄/キレなかったけど、キレたかもしれなかった
032……宇田智子/富士山
040……吉田亮人/写真で食っていくということ
046……野村佑香/今日もどこかの空の下
052……大澤 聡/流れさる批評たち──リサイクル編
062……若杉 実/マイ・ブラザー・アンド・シンガー
070……中野 純/つぶやかなかったこと
076……谷亜ヒロコ/よくテレビに出ていた私がAV女優になった理由
080……東間 嶺/ウィー・アー・ピーピング
086……小川たまか/南の島のカップル
092……西牟田 靖/「報い」
098……久保憲司/スキゾマニア
106……藤森陽子/バクが夢みた。
112……井上健一郎/路地という都市の余白
116……我妻俊樹/イルミネ
120……木村重樹/40年後の〝家出娘たち〟
126……諸星久美/アンバランス
132……大西寿男/before ──冷麺屋の夜
142……辻本 力/雑聴生活
146……友田 聡/中国「端午節」の思い出
150……出門みずよ/苦界前
154……荒木優太/人間の屑、テクストの屑
160……山田 慎/パンと音楽と京都はかく語りき
164……三浦恵美子/子供部屋の異生物たち
172……柳瀬博一/ぼくの「がっこう」小網代の谷
182……長谷川町蔵/サードウェイブ
190……円堂都司昭/『漂流教室』の未来と過去
196……かとうちあき/のようなものの実践所「お店のようなもの」
200……須川善行/死者と語らう悪徳について 間章『時代の未明から来たるべきものへ』「編集ノート」へのあとがき
206……後藤ひかり/南極の石を買った日
210……武田 徹/『末期の眼』から生まれる言葉
216……美馬亜貴子/二十一世紀鋼鉄の女
222……多田洋一/幻アルバム
234……【参加者のプロフィール】
写真:徳吉久
アートディレクション:吉永昌生
校正:大西寿男
編集/発行:多田洋一
取次:株式会社JRC(人文・社会科学書流通センター)
http://www.jrc-book.com/list/yoichijerry.html
【参照記事】
<「新文化」オンライン 2015年3月23日>
http://www.shinbunka.co.jp/news2015/03/150323-03.htm
<おまけ〜ノベライズ:ウィッチンケア第6号>
<ウィッチンケア第6号と88の言葉>
※小誌は全国の主要書店でお取り扱い可能/お買い求めいただけます。
(見つからない場合は上記ISBNナンバーでお問い合わせください
★【書店関係の皆様へ】ウィッチンケアは(株)JRCを介して全国の書店での取り扱い可能。第5号だけでなくBNも下記URLのPDF書類で注文できます。どうぞよろしくお願い致します!
http://www.jrc-book.com/order%20seet/yoichi/yoichijerry.pdf
http://www.jrc-book.com/list/yoichijerry.html
※BNも含めamazonでも発売中!
http://amzn.to/1BeVT7Y